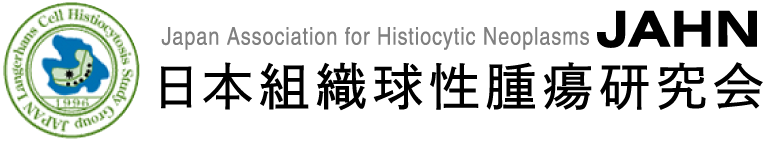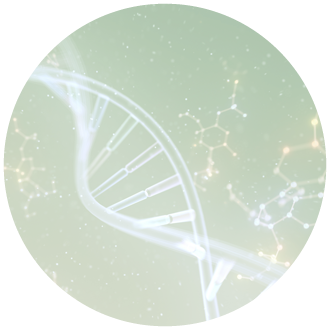最新学術情報
第80回 最新学術情報
1)「ランゲルハンス細胞肉腫は、臨床的、生物学的、予後的に多様な「悪性」組織球症である:文献から得られた88症例の系統的レビュー」
Langerhans cell sarcoma is a clinically, biologically, and prognostically heterogeneous "malignant" histiocytosis: a systematic review of 88 cases from the literature.
Dezzani A,et al. Virchows Arch. 2025 Dec;487(6):1195-1207.
悪性組織球症は、臨床的および組織病理学的に悪性の特徴を示す稀な組織球性腫瘍である。こうした疾患の一つであるランゲルハンス細胞肉腫(LCS)は、LCHといくつかの組織病理学的特徴を共有しているが、明らかに悪性度の高い細胞学的特徴を示すことで区別される。LCSに関する文献は、ほとんど症例報告と少数の総説に限られており、病理分類の完全な見直しは行われていない。本研究は、LCSに関する知識のギャップを埋め、潜在的な予後因子を探り、将来の治療研究の指針となり得る、より良い患者層別化のための臨床的サブ分類を提案することを目的とした。PRISMAガイドラインに従って、文献の系統的レビューを実施した。対象となる症例の臨床的および病理学的特徴のデータを収集した。記述統計、関連統計、生存分析は、R Studioを用いて行った。88例のコホートを分析し、その大多数は皮膚とリンパ節病変を伴う多臓器型の成人男性であった。pERK経路の遺伝子変異を約半数に認めた。他の造血腫瘍の合併が有意な予後不良因子であったが(p=0.0017)、全体の予後は不良であった。さらに、原発例では、単一臓器型と多臓器とで有意な差を認めた(p=0.012)。治療法は非常に多様であったが、統計解析により、病変の広がりに応じた治療が妥当性であるという知見が得られた(例:局所腫瘤を手術のみで治療すると完全寛解に至る頻度が高い, p=0.0002)。本研究から、LCSの病理学および予後因子に関する広範な分析が得られ、LCSをLCHやその他の組織球症と鑑別することの重要性、病変の広がりを定義し治療管理するための統一した指針を作成することの重要性が明らかとなった。
2)「Erdheim-Chester病における心血管変性:有病率、疾患重症度、転帰」
Cardiovascular degeneration in Erdheim-Chester disease: prevalence, burden, and outcomes.
Tawfiq RK, et al. Blood Adv. 2025 Dec 9;9(23):5988-6000.
Erdheim-Chester病(ECD)は、まれな全身性の組織球性腫瘍であり、心血管リスク因子や心臓疾患などの心臓の合併症は疾患の重症度に大きくに関わっているが、その役割は十分に解明されていない。本研究では、心臓病変のあるECD(ECD-C)と心臓病変のないECD(ECD-noC)の有病率、特徴、予後を評価し、年齢や性別などを一致させた対照群と心臓疾患の負担を比較した。1990年~2021年に三次医療機関でECDと診断された患者を対象とし、心臓病変は放射線画像検査を用いて中央で評価した。年齢、性別、BMI、喫煙歴を一致させた非ECDの対照群と心臓疾患の重症度を比較した。ECDの104例中39例(37%)に心臓病変を認めた。ECD-C群はECD-noC群と比較して、高血圧(67% vs 46%)、高脂血症(67% vs 40%)、心不全(36% vs 8%)、心嚢液貯留(28% vs 2%)の発生率が高かった。非ECD対照群と比較し、ECD群は冠動脈疾患(20% vs 7%)、心不全(18% vs 4%)、降圧薬使用(55% vs 40%)が多かった。特に、ECD-C群はECD-noC群と比較して、一次治療による無増悪生存率(PFS)が劣っていた(5年PFS, 28.3% vs 70.5%)。これらの知見は、心臓病変ありと臨床的に診断されていない例でも、ECDにおける心血管リスク因子および心臓疾患の重要性を浮き彫りにしている。特筆すべきは、この心臓疾患の負担がECD-C患者ではECD-noC患者と比較して大きいことである。我々の知見は、患者の予後を改善するために、包括的な心臓リスク評価および管理戦略の必要性を強調している。
3)「成人Rosai-Dorfman病の頭蓋内症状:327症例の系統的レビューとIPDメタアナリシス」
Intracranial manifestations of adult Rosai-Dorfman disease: a systematic review and IPD meta-analysis of 327 cases.
Perez-Chadid DA, et al. Acta Neurochir (Wien). 2025 Dec 6;167(1):316.
Rosai-Dorfman病(RDD)はまれな非ランゲルハンス細胞性組織球症で、約5%の例に中枢神経浸潤を認め、多くは頭蓋内に病変が生じる。小児例の報告は増えているが、成人の頭蓋内RDDについては依然として十分に解明されていない。PRISMAガイドラインに従ってシステマティックレビューと個々の症例データのメタアナリシスを行い、成人頭蓋内RDDの疫学、臨床所見、病理、診療戦略、転帰を明らかにした。PubMed、Scopus、Cochrane Libraryで、症例報告、症例シリーズ、観察研究を含めて、18歳以上で組織学的診断された例を検索した。年齢・性別、症状、画像所見、組織病理所見、治療、転帰に関するデータを抽出した。主要評価項目は治癒と無再発生存期間(RFS)とし、リスク比(RR)と95%信頼区間(CI)はランダム効果モデルを用いて計算した。 186件の研究から327例が適格基準を満たした。年齢は中央値43.6歳(範囲:18~83歳)、男性が70.9%と多かった。最も多かった症状は、頭痛(35.2%)、次いで痙攣または意識喪失(28.7%)、視覚障害(26.9%)であった。病変は、典型的にはテント上の脳実質内(52.9%)または脳実質外(20.5%)に認めた。93.6%の例に手術が行われ、45.3%の例で全摘出が可能であった。追跡期間の中央値18.8か月で、37.9%が完全治癒、46.8%が部分治癒、15.3%が再発し、RFSは中央値12か月であった。全摘出は治癒と強く関連していた(相対リスク0.26, 95%信頼区間0.19-0.37)。一方、テント上脳実質内病変(相対リスク0.56, 95%信頼区間0.41-0.75)および病変周囲浮腫(相対リスク0.65, 95%信頼区間0.47-0.89)は予後不良因子であった。これらの知見は、成人頭蓋内RDDは主に中年男性に発症し、占拠性病変症状を呈し、予後は病変部位に依存することを示している。治癒の可能性が最も高い治療は全摘出であるが、再発は依然として多く、長期間の経過観察が必須である。
4)「リソソームキャリアSLC29A3は、抗菌シグナル伝達をサポートし、マウス樹状細胞においてTRPML1を活性化することでオートファジーを促進する」
The lysosomal carrier SLC29A3 supports antibacterial signaling, and promotes autophagy by activating TRPML1 in murine dendritic cells.
Netting DJ, et al. Proc Natl Acad Sci U S A. 2025 Dec 2;122(48):e2511539122.
溶質キャリア(SLC)29A3は、リソソームからヌクレオシドを細胞質へ輸送し、溶質の恒常性を維持し、細胞プロセスのための代謝中間体を供給する。 SLC29A3の機能喪失変異は、組織球症、過剰炎症、免疫不全を特徴とするH症候群を引き起こす。マウスにおけるH症候群およびSLC29A3欠損では、様々な細胞系の機能不全が関与しているが、過剰炎症および免疫不全を引き起こすメカニズムは完全には解明されていない。注目すべきことに、最も効率的な抗原提示細胞であり、自然免疫と獲得免疫を繋ぐ主要な細胞である樹状細胞が果たす役割は未だ不明である。本研究では、マウス樹状細胞において、SLC29A3が細菌捕捉後にファゴソームにリクルートされ、ファゴソームpH恒常性を維持し、IL-6、IL-12、pro-IL-1β、およびCCL22の産生に最適な抗菌性ファゴソームシグナル伝達を確保することを明らかにした。さらに、SLC29A3はMHC-II分子への抗原提示を促進し、獲得疫応答を開始させる。特に、SLC29A3はリソソームカルシウムチャネルTRPML1の活性をサポートし、転写因子TFEBの核移行を促進し、主要な抗炎症機構であるオートファジーを誘導する。SLC29A3欠損マウス樹状細胞において、ヒト野生型SLC29A3を過剰発現させると、細菌貪食に対するサイトカイン産生が回復するが、輸送変異体であるG437Rを過剰発現させても回復しない。これは、SLC29A3の輸送活性がファゴソームシグナル伝達の駆動に必要であることを示唆している。本データは、SLC29A3が効果的な抗菌シグナル伝達と抗原提示を促進し、オートファジーを誘導することで、樹状細胞における免疫機能をサポートし、制御することを示唆している。この研究結果はまた、SLC29A3 が TFEB を活性化する TRPML1 依存性のメカニズムを明らかにし、ファゴソーム抗菌シグナル伝達、TFEB 活性化、およびオートファジーの欠陥が SLC29A3 疾患における免疫不全および過剰炎症に寄与する可能性があることを示唆している。
5)「成人におけるRosai-Dorfman-Destombes病の臨床病理学的スペクトラム:16例の解析」
The Clinicopathologic Spectrum of Rosai-Dorfman-Destombes Disease in Adults: An Analysis of 16 Cases.
Trinder M, et al. Eur J Haematol. 2025 Dec;115(6):555-564.
Rosai-Dorfman-Destombes病(RDD)は、リンパ節およびリンパ節外組織に活性化した組織球が集積することにより、多様な臨床症状が出現する稀な組織球増殖症である。特にリンパ節以外の病変から組織検体を採取した場合、リンパ節病変で観察される組織学的特徴が顕著でないことがあるため、診断が見逃される可能性がある。2015年~2025年にカナダのバンクーバーでRDDと診断された16例の成人例を調査した。RDDに関連する病変の最初の生検から病理診断が確定までに60日を超え、かつ、2回以上の生検が必要であった症例を診断困難例とした。16例中8例(50%)が診断困難例であった。RDDと確定診断するために必要とした生検回数は中央値2.0 (四分位範囲: 2.3) で、5例は3回以上の生検を必要とした。最終診断までに要した期間は、診断困難例以外では平均12日(IQR: 15日)、診断困難例では240日(IQR: 138日)であった。特に、診断困難症例では、非典型的な解剖学的部位からの検体採取(62.5% vs. 37.5%)、最適とは言えない病理学的検体採取法(例:細胞診)(87.5% vs. 25.0%)、血液リンパ系病理専門医への未相談/遅れ(87.5% vs. 25.0%)が多く見られた。本研究から、リンパ節外性RDDは臨床的多様性が極めて高いこと、血液リンパ系病理学の専門知識が診断において極めて重要であることが明らかとなり、早期にRDDを鑑別診断から除外することを避けるために、非典型的な組織球浸潤に対しては免疫組織化学染色を積極的に活用することなどが必要であることを示唆している。
6)「悪性組織球性腫瘍におけるPD-L1発現と免疫チェックポイント阻害薬療法への反応」
PD-L1 expression and response to immune checkpoint inhibitor therapy in malignant histiocytic neoplasms.
Ravindran A, et al. Leuk Lymphoma. 2025 Dec;66(14):2675-2684.
悪性組織球性腫瘍は、確立された有効な治療法のない悪性度の高い悪性腫瘍である。最近の研究では免疫チェックポイント阻害剤の有効性が示唆されているが、反応性を予測することはできない。26例の悪性組織球性腫瘍を分析し、PD-L1発現頻度と臨床病理学的相関を調べた。腫瘍細胞のPD-L1評価は、手動で陰性群と陽性群(≥ 1%)に分類した。診断時の年齢は中央値59歳で、73%がPD-L1陽性であった。PD-L1発現が50%以上の患者は、PD-L1が50%未満の患者と比較して全生存率が良好であった(100% vs 42%, P値: 0.0324)。6例の悪性組織球性腫瘍に対する免疫チェックポイント阻害薬の全奏効率(ORR)は50%であった。包括的な文献レビューにより、免疫チェックポイント阻害薬で治療された14例の悪性組織球性腫瘍患者のORRは64%であることが明らかになった。 免疫チェックポイント阻害薬治療を受けた、本コホートの6例と文献から抽出した症例の計20例では、奏効群は非奏効群と比較してPD-L1発現の中央値が高かった(88% vs 30%, P値: 0.0737)。免疫チェックポイント阻害薬は悪性組織球性腫瘍に対して有望であるが、化学療法/放射線療法併用の有無による長期的な持続性と有効性を解析するには、より大規模なコホートを体系的に調査する必要がある。
7)「小児LCHにおいて末梢免疫指標は疾患進行や再発の予測因子となる」
Peripheral immune indicators and their predictive value in disease progression or relapse of pediatric Langerhans cell histiocytosis.
Li HL, et al. J Pediatr (Rio J). 2025 Nov-Dec;101(6):101466.
【目的】LCHは、炎症性微小環境が疾患の発症および進行に重要な役割を果たす稀な炎症性骨髄性腫瘍である。末梢血中リンパ球サブセットやサイトカインによって予後を予測できるかは依然として不明である。【方法】330例の小児LCHにおいて診断時の末梢血リンパ球サブセットおよび血清サイトカインを後方視的に解析した。免疫プロファイルが、病期、臨床イベント、生物学的特徴により異なるかを比較した。無増悪生存期間(PFS)に与える因子を単変量モデルおよび多変量モデルを用いて検証した。【結果】末梢免疫プロファイルは病期によって異なった。多臓器型リスク臓器浸潤陽性(MS RO+)例では、総T細胞およびTh1細胞が少なく、CD4⁺ T細胞およびB細胞が多く、IL-6、IL-10、IFN-γが高かった。疾患進行や再発した例で同様のパターンを認め、死亡例では特にIL-10が高かった。開発コホートでは、T細胞、B細胞、CD4⁺ T細胞、CD8⁺ T細胞、およびTh1細胞の割合、CD4/CD8およびTh1/Th2比、IL-6およびIL-10値が進行/再発の予測因子となり、Youden法によるカットオフ値により2分され、PFSに明確な差を認めた。多変量Cox検定では、IL-6、IL-10、Th1/Th2比、リスク臓器浸潤、および6週目の治療反応が独立した予測因子であり、優れた予測能力を持つノモグラムモデルが構築された。単一臓器LCHにおいては、免疫指標は予後予測因子とはならなかった。103例を対象とした外部検証コホートにより、リスク層別化とモデルの性能が確認され、PFSの予測値が非常に正確であることが示された。【結論】診断時の末梢血リンパ球サブセットとサイトカインは、小児LCHにおいて予後予測因子であった。IL-6、IL-10、およびTh1/Th2プロファイルはリスク層別化を裏付け、治療計画策定に有用な情報となる可能性がある。
8)「ナノ粒子増強細胞診: Erdheim-Chester病の迅速診断における2025年の画期的な進歩」
Nanoparticle-enhanced cytology: a 2025 breakthrough for rapid diagnosis of Erdheim-Chester disease.
Butt A, et al. Ann Med Surg (Lond). 2025 Nov 14;88(1):982-983.
Erdheim-Chester病(ECD)は、CD68陽性、CD1a/S100陰性の組織球を特徴とする極めて稀な非ランゲルハンス細胞性組織球症で、BRAF V600Eやその他のMAPK経路の遺伝子変異をしばしば伴う。診断は、非特異的な症状と侵襲的な生検によりなされ、発症後数年経過して診断されることがしばしばあり、依然として困難である。表面増強ラマン分光法を含むナノ粒子増強細胞診は、2025年には有望な画期的な技術として登場し、細胞診スライド上の単一分子を検出できる高い感度があり、複数のバイオマーカーを同時に検出することも可能である。PETに用いられるCu-Macrinなどのナノ粒子ベースのイメージング剤は、マクロファージに富む病変に対して高い特異性を示し、ナノ粒子アッセイはBRAFV600Eなどの血中循環腫瘍DNAの捕捉を改善する。これらのナノ粒子ベースの方法をAI駆動型画像解析と統合することにより、現在のECDの診断における課題を克服し、より早期に、より低侵襲に、より正確に診断できる可能性がある。ナノ粒子ベースの診断プロトコルの標準化と継続的な研究は、これらの新しい技術を検証し、臨床実践に応用するために不可欠である。
9)「Erdheim-Chester病におけるダブラフェニブの有効性と安全性」
Efficacy and safety of Dabrafenib in Erdheim-Chester disease.
Liu ZZ, et al. Ann Hematol. 2025 Nov;104(11):5669-5676.
BRAFV600E変異陽性のErdheim-Chester病(ECD)に対するダブラフェニブの有効性と安全性を評価することを目的とした。2021年12月~2025年2月に北京協和医学院病院と中国医学科学院癌病院において、ダブラフェニブ治療を1か月以上受けた例を後方視的に解析した。全例にダブラフェニブ75~150 mgが1日2回投与された。治療反応は放射線学的に判定し、客観的奏効率(ORR)を評価した。BRAFV600E変異を有する20例のECDが対象となった(女性7例、男性13例、年齢の中央値51.5歳[範囲:9~72歳])。最も頻度の高い浸潤臓器は骨(16例、80.0%)で、次いで肺(11例、55.0%)、腎周囲(10例、50.0%)、中枢神経系(9例、45.0%)であった。評価可能であった17例におけるORRは100.0%(95% CI, 80.5-100.0%)で、5例(29.4%)が完全奏効、12例(70.6%)が部分奏効であった。追跡期間の中央値は19.5か月であった。病勢進行および死亡例はなかった。6例(30.0%)がダブラフェニブの投与を中止したたが、その理由は、経済的制約(3例)、有害事象(1例)、患者の意向(1例)、放射線学的奏効にもかかわらず症状の改善が不十分(1例)であった。18か月時点の無イベント生存率および全生存率は、それぞれ68.7%(95% CI, 50.7%-93.3%)、100.0%であった。コホート全体で多く認めた有害事象(AE)は、関節痛(7例、35.0%)、発熱(6例、30.0%)、発疹(4例、20.0%)で、グレード3~4のAEは認めなかった。ダブラフェニブは、BRAFV600E変異陽性のECDに対して、有効性は高く、安全性は許容可能である。
10)「小児LCHにおける治療前18F-FDG PET代謝パラメータの応用」
Application of pretreatment 18F-FDG PET metabolic parameters in children with Langerhans cell histiocytosis.
Wen X, et al. Ann Hematol. 2025 Nov;104(11):5635-5645.
小児LCHにおいて、治療前の18F-FDG PET/CTの代謝パラメータにより、cfBRAFV600E変異の検出および予後を予測できるかどうかを評価することを目的とした。2020年9月~2024年3月に治療前に18F-FDG PET/CT検査を受けた新規に診断された64例の小児LCHを後方視的に解析した。最大標準化集積値(SUVmax)、腫瘍対肝臓標準化集積値比(SUVRliver)、腫瘍対骨髄標準化集積値比(SUVRBM)、総代謝腫瘍容積(tMTV)、総病変解糖能(tTLG)などの代謝パラメータを測定した。代謝パラメータとcfBRAFV600E変異の検出との関連性はROC曲線解析を用いて評価した。 PFSはカプランマイヤー法とCox比例ハザード回帰を用いて評価した。cfBRAFV600E変異は22例(34%)で検出された。変異検出例は、全ての代謝パラメータが有意に高かった(すべてP<0.05)。SUVRliverは、判定能が最も高く(AUC 0.806、最適カットオフ値6.9)、次いでtMTV(AUC 0.792、最適カットオフ値6.2 cm3)であった。多変量ロジスティック回帰分析では、変異の検出を予測する3つの独立した因子:若年(オッズ比[OR]=0.595, P=0.001)、高tMTV(OR=26.760, P=0.001)、進行した臨床病期(OR=7.199, P=0.005)が同定された。追跡期間の中央値25.2か月で、多変量Cox回帰分析において、tMTVはPFSの最も強力な独立した予測因子であった。tMTVが14.66 cm³以上の例は、それより低値の例と比較して有意に予後が悪かった(log-rank P<0.001)。小児LCHにおいて、治療前の18F-FDG PET/CT代謝パラメータによって、cfBRAFV600E変異の検出と臨床転帰の両方を予測することが可能である。SUVRliverとtMTVは変異検出の予測において優れた判定能を示し、tMTVは独立した予後予測因子である。これらの非侵襲性バイオマーカーは、リスク層別化と治療計画に役立つ可能性がある。
第79回 最新学術情報
最近掲載されたLCH関連の論文抄録を紹介します。
1)「動脈内化学療法による難治性腫瘤性および神経変性組織球症の治療」
Refractory Tumorous and Neurodegenerative Histiocytosis Treated With Intra-Arterial Chemotherapy.
Ramos A,et al. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2025 Nov;12(6):e200495.
【背景と目的】組織球症は、神経学的障害を伴う多様な造血疾患である。近年、MAPK経路阻害薬が臨床的および画像的に奏効することが報告されているが、一部の患者では、これらの治療に不耐応であったり、孤発性または難治性の神経・眼・頭頸部の病変であったりする。動脈内化学療法は様々な腫瘍において良好な反応が報告されているが、組織球症においては治療効果や転帰は検討されていない。【方法】生検で頭頚部病変の組織球症と診断された患者に対し、血管造影、選択的カテーテル法、メルファランの動脈内注入による外来治療を行った。標的動脈は病変部位に応じて決定した。必要に応じて放射線学的検査(PET/CT、CT、MRI、眼科超音波検査、光干渉断層撮影)や定量化された機能評価(視力、言語、平衡感覚)による追跡調査を行った。放射線学的および機能的奏効率(完全奏効または部分奏効)に加え、治療後の病勢進行の率も調査した。【結果】18例が計74回の治療を受けた。放射線学的に評価可能な腫瘤性病変のある14例のうち10例(71%)が部分奏効または完全奏効を示し、残る4例は病勢安定を示した。その後、14例中3例(21%)は放射線学的に病勢進行を示した。機能的に評価可能な13例(神経変性組織球症の6例を含む)のうち、12例(92%)が機能改善を示した。その後、13例中7例(54%)は病勢進行による機能悪化を示した。術中合併症は認めなかった。治療後、3例が入院を必要とし、うち1例はメルファランに対するアレルギー反応であった。【考察】腫瘤性および神経変性の組織球症に対して、メルファラン動脈内投与は安全かつ非常に有効な治療法であり、神経機能の改善が期待される。更なる研究により、この介入に最も適した症例が明らかになる可能性がある。この新しい治療法は、神経系および眼の病変を伴う難治性の腫瘤性ならびに神経変性組織球症の治療において、革新に治療方針を根本的に変える可能性がある。動脈内化学療法は新規の治療法であり、今後の研究では、この治療法の有効性を他の神経系や眼、頭頸部のがんに対しても検討する必要がある。【エビデンスの分類】本研究は、腫瘤性または神経変性組織球症に対して、選択的血管造影カテーテル法とメルファラン動脈内注入が放射線学的および機能的改善をもたらすというクラスIVのエビデンスを示している。
2)「小児LCHにおける全身MRIとFDG-PET/CTとの比較」
Whole-body MRI in Pediatric Langerhans Cell Histiocytosis-A Comparison With FDG-PET/CT.
Baijal N, et al. J Pediatr Hematol Oncol. 2025 Nov 1;47(8):e398-e409.
【目的】小児LCHでは、病期分類や治療効果判定にFDG-PET/CTが用いられる。全身MRIは、電離放射線を使用しないため、全身画像を繰り返し撮影する際の代替検査として有用である。小児LCHの病期分類および治療効果判定において、全身MRIとFDG-PET/CTを比較することを目的とした。【方法】本研究は、倫理委員会の承認を得て、2021年8月~2023年3月に、最先端医療施設において実施された前方視向的コホート研究である。生検でLCHと診断された18歳以下の症例を対象に、病期分類または治療効果判定のためにFDG-PET/CT検査を行い、その際に全身MRI検査も実施した。 FDG-PET/CTを基準として、病期および治療効果判定における診断精度と一致率を算出した。治療方針への影響および画質についても評価した。【結果】LCH 11例(女性:男性=5:6、平均年齢6.95歳)を対象とした。診断精度および一致率は、診断時はそれぞれ90.6%および80%(κ係数:0.69)、追跡調査時はそれぞれ96%および83.3%(κ係数:0.74)であった。11例中2例で全身MRI検査に基づいて治療方針が変更された。画質とアーチファクトの評価(最低1, 最高5の5段階)をDWIとSTIRの11スキャンで行い、画像はそれぞれ3.91±1.30と4.82±0.40、アーチファクトそれぞれ3.82±1.33と4.55±0.52であった。【結論】LCH患者における全身MRIの診断精度とFDG-PET/CTとの一致率は、診断時および追跡調査時ともに高かった。全身MRIは、小児LCHにおいてFDG-PET/CTに代わる、放射線を使用しない画像検査となり得る。
3)「小児LCHにおける分子標的療法:有効性を維持しながら長期曝露を最小限に抑える新たな戦略の解説」
Targeted Therapy in Pediatric Langerhans Cell Histiocytosis: Describing a Novel Strategy to Minimize Long-Term Exposure While Maintaining Efficacy.
Wojciechowska N, et al. Pediatr Blood Cancer. 2025 Nov;72(11):e32016.
【背景】LCHは、MAPK経路の活性化によって引き起こされる稀な悪性腫瘍であり、しばしばBRAF V600E変異を伴う。MEK阻害剤であるトラメチニブを用いた分子標的療法は、従来の化学療法に代わる有望な選択肢である。【方法】2020年~2024年に、再発時または第一選択療法としてトラメチニブによる治療を受けた患者の診療録を後方視的に解析した。【結果】小児15例が、診断時(6例)、再発時(7例)、化学療法不耐容(2例)でトラメチニブを投与された。MAPK経路の変異が11例で同定された。治療開始時の年齢は中央値5歳(範囲:0.1~16.5歳)であった。注目すべきことに、これらのうち5例は1歳未満でトラメチニブの投与を開始した。治療期間は中央値2.2年(範囲:0.1~4.7歳)であった。15例全てが良好な反応を示し、成長と発達に関する懸念はなかった。副作用は発疹(40%)と下痢(13%)であったが、いずれも軽度で、一時的な用量調節で管理できた。自己離脱型投与戦略により、病勢コントロールを維持しながら、薬剤暴露期間を最小限に抑えることができた。【結論】本データは、トラメチニブは、小児LCHに対する安全かつ有効な治療法であり、幅広い有効性と忍容性があることを示唆している。しかしながら、これらの知見を確認し、標的治療プロトコルを改良するためには、前方視的研究が必要である。
4)「Erdheim-Chester病の分子生物学的全体像の解明:メチロームとトランスクリプトームの統合による新たな知見」
Unraveling the molecular landscape of Erdheim-Chester disease: new insights from methylome and transcriptome integration.
Cerván-Martín M, et al. Leukemia. 2025 Nov;39(11):2758-2766.
Erdheim-Chester病(ECD)は、多様な臨床症状を特徴とする稀な組織球症である。ECDには体細胞変異が関与していることが知られているが、その病因は未だ十分に解明されていない。本研究では、ECDに関与する新たな分子メカニズムを、初めてメチロームとトランスクリプトームの統合解析によって明らかにすることを目指した。ECD 137例と対照 410名から末梢血サンプルを採取した。ゲノムワイドDNAメチル化解析とトランスクリプトーム解析を行い、様々なWeb上のバイオインフォマティクスツールを用いた機能的in silico解析を実施した。その後、メチロームとトランスクリプトームのデータを統合し、既承認薬再開発の戦略を用いた。その結果、ECDに関連する2,511のメチル化部位と1,484の発現レベルが異なる遺伝子が見出された。統合解析により、ECD患者における29個の遺伝子発現レベルを制御する、46個のDNAメチル化パターンの変化が同定され、免疫応答と腫瘍形成に関与する主要遺伝子が明らかになった。注目すべきことに、本研究の結果、B細胞とNF-κBシグナル伝達経路がECD病態に関連する新たな因子であることが示された。最後に、既承認薬再開発の戦略により、ECD患者に対する潜在的な治療選択肢が特定された。結論として、本研究はECDの分子基盤の理解において重要な進歩であり、ECD病態に関与する新たな細胞型と経路を提示し、臨床管理の新たな方向性を示唆している。
5)「Rosai-Dorfman病の鼻病変:臨床症状と治療成績」
Nasal Presentations of Rosai-Dorfman Disease: Clinical Manifestation and Treatment Outcomes.
Xu H, et al. Ear Nose Throat J. 2025 Nov;104(11):NP770-NP778.
【目的】Rosai-Dorfman病(RDD)の鼻病変に対するエビデンスに基づいた治療戦略は未だ確立されていない。鼻RDDの臨床症状、治療、治療成績を解析することを目的とした。【方法】2014年~2021年に、当科で鼻RDDと診断された患者の診療記録を後方視的に解析した。【結果】計26例が対象となり、女性が著しく多かった(2.25:1)。最も頻度の高い症状と病変部位は、それぞれ鼻閉(31%)と鼻腔(73%)であった。生検回数は平均1.5回(範囲:1~3回)であった。組織球はS100およびCD68陽性、CD1a陰性で、細胞内細胞嵌入現象(emperipolesis)が多くみられた。追跡期間は平均34か月(範囲:3~87)であった。1例が鼻腔の小細胞性B細胞リンパ腫を併発し、化学療法・放射線治療後に完全寛解した。推奨される治療は、内視鏡的切除(92%)と経口コルチコステロイド(21%)であった。切除可能な病変を可能な限り完全に切除する手術が行われた。コルチコステロイドにより、ほぼ100%が寛解した。再発患者のうち、2例は全奏効を達成し、1例はその後に切除術を受けたが進行期のままであった。郭清生検のみを受けた2例は、それぞれ経口コルチコステロイド投与と、レナリドミドとデキサメタゾンの併用療法に反応した。【結論】鼻腔と副鼻腔のびまん性病変、さらには鼻頭蓋底、咽喉頭、眼窩、海綿静脈洞に広く浸潤している病変を見たときには、RDDの可能性を考慮する必要がある。特徴的な免疫組織化学染色は診断に有用である。極度の苦痛を伴う例に対する治療として、内視鏡的外科療法が依然として主流である。経口コルチコステロイドは、第一選択治療の補助療法として役立つ。
6)「小児LCHに対するダブラフェニブ標的療法の有効性と安全性:システマティックレビューとメタアナリシス」
Efficacy and safety of dabrafenib-targeted therapy for pediatric langerhans cell histiocytosis: a systematic review and meta-analysis.
Lu Y, Ye Y, Ren W, Leng X, Dai Y. Transl Pediatr. 2025 Oct 31;14(10):2606-2616.
【背景】LCH患者におけるBRAF遺伝子変異の存在と標的療法は、LCH治療の考え方を変化させ、LCH患者の予後を大きく改善した。しかしながら、小児における標的薬の投与量と投与中止時期に関して統一された基準はない。小児LCHに対するダブラフェニブの治療可能性と有害事象に関するより強固な理解を提供するために、臨床試験および研究データを収集した。【方法】小児LCHに対するダブラフェニブの有効性と安全性を評価するため、5つの電子データベースを検索して9件の研究を見出し、より包括的で信頼性の高い結論を導き出すために、PRISMA 2020チェックリストに基づいてデータを統合し、システマティックレビューとメタアナリシスを実施した。【結果】本研究プロトコルはPROSPERO(CRD420251046705)に事前登録した。解析の結果、ダブラフェニブは小児LCHの治療成績を有意に改善することが示され、客観的奏効率は83%(95%信頼区間70-91%)、病勢制御率は85%(95%信頼区間68-94%)、1年無増悪生存率は80%(95%信頼区間45-95%)で、有害事象は管理可能(グレード3以上の有害事象発生率2%)で安全性プロファイルは許容できるものであった。これらの結果は、ダブラフェニブが小児LCH、特にBRAF遺伝子変異を有する症例において有望な治療選択肢となる可能性を示唆している。5つの研究では、末梢血中cell free BRAFV600 E(cfBRAFV600 E)陽性率もモニタリングされており、その値は49.7%(95%信頼区間:28.7-70.8%)であった。2歳未満の群では、奏効率は92%(95%信頼区間:76-100%)に達した。【結論】この結果は、特に2歳未満の小児LCHの治療にダブラフェニブを組み込むことを支持しており、これらの結果を検証し、その長期的な効果を探求し、最終的には患者アウトカムの向上とこの困難な疾患の負担軽減を目指するための、更なる前方視的研究の必要性が明らかとなった。
7)「SHH/YAP経路依存性ヒト組織球性肉腫オルガノイドの樹立」
Establishment of human histiocytic sarcoma organoids dependent on the SHH/YAP pathway.
Yoshimura Y, et al. Hum Cell. 2025 Oct 9;38(6):175.
組織球性肉腫は、成熟組織球の免疫表現型を特徴とする極めて稀で悪性度の高い悪性腫瘍である。その悪性化のメカニズムは未だ十分に解明されておらず、その結果、効果的な治療法の開発は限られている。切除された組織球性肉腫組織を、改良気液界面オルガノイド法を用いて培養し、継代培養した後、NOD-scid IL2Rgnullマウスに異種移植した。異種移植されたオルガノイドによって形成された腫瘍は、元の腫瘍と、組織学的および遺伝学的類似性を維持していた。ゲノム解析により、Sonic Hedgehogシグナル伝達経路の活性化と、Hippo経路の重要なエフェクターであるYes関連タンパク質1の増幅が明らかになった。そこで、オルガノイドに対する、Sonic Hedgehog 阻害剤ビスモデギブとYes関連タンパク質1阻害剤ベルテポルフィンの感受性を評価した。両剤は培養オルガノイドに対してin vitroで強力な抗腫瘍活性を示した。このモデルは、この希少悪性腫瘍の分子病理を解明し、標的治療の開発を加速するための貴重な前臨床の研究基盤となる。
8)「小児LCHにおける18F-FDG PET/CT:BRAFv600e変異および病期分類との関連」
18F-FDG PET/CT in pediatric langerhans cell histiocytosis: relation to BRAFv600e mutation and risk stratification.
Ji X, et al. Eur J Radiol. 2025 Oct;191:112361.
【目的】BRAFv600eは、小児LCHにおいて高リスク所見および治療反応不良と関連する。病期分類における18F-FDG PET/CTの役割を評価し、LCHにおける18F-FDG集積とBRAFv600e変異との関連を解析することを目的とする。【方法】新規に診断された114例の小児LCHの治療前18F-FDG PET/CT画像を後方視的に解析した。画像所見と臨床病理学的所見との関連を解析した。【結果】PET/CT画像によって、47例(41.2%)で病期が変更された。PET/CTにより追加で検出された病変の中で最も多かったのは、リンパ節と胸腺であった。CRP高値は、病期の上昇と関連していた(オッズ比:2.737, 95%信頼区間: 1.193-6.276, p=0.017)。CRP高値の例はCRP正常値の例と比較し、病変のSUVmaxが有意に高かった(10.2±4.7 vs. 7.3±3.6, p=0.001)。70例でBRAFv600e変異の有無が検査された。BRAFv600e変異のある例は、18F-FDGの集積が有意に低下していた(SUVmax: 8.2±3.3 vs. 10.8±4.9, p=0.019)。多変量ロジスティック回帰分析の結果、BRAFv600e変異は、SUVmax ≤10.6(オッズ比6.868, 95%信頼区間1.751-26.946, p=0.006)、胸腺浸潤の欠如(オッズ比11.849, 95%信頼区間1.907-73.635, p=0.008)、CRP ≥15.0 mg/L(オッズ比8.062, 95%信頼区間1.538-42.263, p=0.014)と有意に関連していることが明らかとなった。【結論】PET/CT画像によって、約40%の例、特にCRP高値例、において追加の骨外病変を同定される。さらに、18F-FDG PET/CT所見はBRAFv600e変異の有無と有意に関連していたが、信頼区間が広かったため、解釈には注意が必要である。
9)「LCH、Erdheim-Chester病、その他の組織球性腫瘍患者に対するルボメチニブ:単群多施設共同第II相試験」
Luvometinib in patients with Langerhans cell histiocytosis, Erdheim-Chester disease, and other histiocytic neoplasms: a single-arm, multicentre, phase 2 study.
Cao XX,et al. EClinicalMedicine. 2025 Sep 17;88:103486.
【背景】組織球性腫瘍は、高頻度のMAPK経路遺伝子の体細胞変異を特徴とする、多様な血液疾患群である。この単群多施設共同第II相試験では、組織球性腫瘍の成人患者に対する、選択的MEK1/2阻害薬であるルボメチニブの有効性と安全性を評価した。【方法】腫瘍の遺伝子変異を問わず、未治療または再発・難治性の16歳以上の患者を登録し、ルボメチニブ8mgを1日1回、28日サイクルで経口投与した。病勢進行、死亡、許容できない毒性、同意撤回、試験終了まで継続投与した。主要評価項目は全奏効率で、独立評価委員会がPETによる反応基準に基づき評価した。この試験は、chinadrugtrials.org.cn(CTR20221069)およびchictr.org.cn(ChiCTR2300067955)に登録された。【結果】2022年6月27日~2024年2月2日までに、30例が登録され、追跡調査期間は中央値16.2か月(範囲1.5~19.3か月)であった。評価可能な29例のうち、LCHが22例(75.9%)、Erdheim-Chesterが3例(10.3%)、その他の組織球性腫瘍が4例(13.8%)であった。大多数(86.2%)が既治療で、27.6%は3種類以上の化学療法を受けていた。追跡期間の中央値16.2か月において、全奏効率は82.8%(95%信頼区間:64.2~94.2)、奏効までの期間は中央値2.9カ月(範囲:2.6~6.0)、半数以上の患者は奏効が持続していた(奏功期間の中央値は未到達)。12か月無増悪生存率は74.4%(95%信頼区間:49.8~88.2)であった。グレード3以上の治療関連有害事象は13例(43.3%)にみられ、毛包炎(10.0%)、高トリグリセリド血症(10.0%)、血中CPK上昇(6.7%)を複数の例に認めた。治療関連有害事象により治療中止に至った症例はなかった。【解釈】ルボメチニブは、組織球性腫瘍患者に対して、高い奏効率と持続的な奏効、管理可能な安全性プロファイルを示した。
10)「小児LCHにおける胆管病変の超音波所見」
Ultrasound Findings of Bile Duct Involvement in Pediatric Langerhans Cell Histiocytosis.
Wang J, et al. J Ultrasound Med. 2025 Oct;44(10):1741-1749.
【目的】小児LCHにおける胆管病変の超音波所見を解析する。【方法】2016年12月~2023年12月までに、当院で病理学的に小児LCHと診断された42例を後方視的に解析した。全例に胆道系異常を示唆する包括的な臨床データと超音波所見を認めた。肝内および肝外胆管拡張、胆管壁肥厚の程度、周囲の異常エコーを解析した。【結果】超音波検査で肝内および肝外胆管拡張を27例(64%)、胆管壁肥厚を21例(50%)、肝内胆管に沿った低エコー領域を16例(38%)、胆管周囲のエコー輝度の低下を伴うグリソン嚢肥厚を8例(19%)に認めた。【結論】小児胆管炎患者において、超音波検査で様々な程度の胆管拡張または狭窄、胆管壁肥厚、肝臓胆管に沿った異常エコーパターンが認められた場合には、LCHを疑うべきである。
第78回 最新学術情報
1)「視床下部・下垂体病変のあるLCH患者:HEROS研究コホートからの知見」
Patients with langerhans cell histiocytosis and hypothalamic-pituitary involvement: insights from the HEROS study cohort.
Masri Iraqi H, et al. Pituitary. 2025 Sep 26;28(5):104.
【目的】LCHは内分泌系を含む複数の臓器に浸潤する稀な疾患である。この多施設共同研究は、視床下部/下垂体病変のあるLCH患者の特徴を明らかにすることを目的とした。【方法】欧州神経内分泌学会の希少病因観察(HEROS)研究を通じて、LCHのような稀な下垂体疾患の患者を研究対象として募集した。性別・年齢、主症状、内分泌ホルモン欠乏状況、画像検査、治療、転帰のデータを収集した。【結果】48例(男性58%)が研究対象となった。診断時年齢は22 ±16.1歳で、58%は診断時年齢が18歳を超えていた。平均追跡期間は15.8 ±10.6年で、初発病変は46%が骨病変、42%が肺病変で、5例は偶然診断された。診断時に、69%は抗利尿ホルモン欠乏症、42%は中枢性性腺機能低下症、25%は中枢性甲状腺機能低下症、12.5%は中枢性副腎皮質機能低下症を認めた。41例でMRI検査が行われ、そのうち73%に下垂体後葉/下垂体茎に病変を認めた。1例のみに視覚障害を認めた。主に下垂体以外の病変の生検により、全例が組織病理学的に確定診断されていた。5例が経頭蓋生検を、2例が経蝶形骨洞生検を受けていた。追跡調査中、27%に新たな抗利尿ホルモン欠乏症、5例に新たな下垂体前葉ホルモン欠損症が出現していた。追跡調査期間中、疾患関連死亡は認めなかった。【結論】視床下部/下垂体病変のあるLCH患者は、長期追跡調査中、臨床的に安定していた。しかし、診断後数年を経て新たなホルモン欠損症が出現する可能性があり、最終的に多くの患者に抗利尿ホルモン欠乏症を認める。
2)「Erdheim-Chester病における症状、未充足の必要な支持療法、生活の質:患者登録コホートの経時的解析」
Symptoms, unmet needs, and quality of life in Erdheim-Chester disease: A longitudinal registry-based analysis.
Marathe PH, et al. Blood Adv. 2025 Sep 9;9(17):4415-4424.
患者報告アウトカムと健康関連QOLを把握することは、包括的で患者中心のがん治療にとって極めて重要である。Erdheim-Chester病(ECD)は、多様な症状が同時に出現し、しばしば診断の遅れを伴う希少がんであるが、患者報告アウトカムと健康関連QOLはともに十分に研究されていない。本研究では、ECD患者における、症状の負担と未充足の必要な支援療法が時間とともにどのように変化するかを評価し、これらの患者報告アウトカムと健康関連QOLとの関連を明らかにすることを目的とした。ECD患者のレジストリ登録コホートにおいて、癌治療の機能的評価-一般版(FACT-G)と検証済みの患者報告アウトカム測定尺度を含む複数の患者報告アウトカム測定ツールを用いて、研究を実施した。患者報告アウトカムとFACT-Gスコアの分布を、記述統計を用いて特徴を明らかにした。レジストリ登録時と登録後12か月の時点において、FACT-G合計スコアを目的変数、患者報告アウトカムを説明変数とし、単変量線形回帰モデルを用いて関連を解析した。12か月時と登録時におけるFACT-G合計スコアの差が、患者報告アウトカムの変化の差と関連するかを、単変量線形回帰分析を用いて解析した。計158例の登録時の平均合計FACT-Gは70.8で、複数のがん患者コホートで通常観察される値よりも低かった。痛みや疲労のレベルが高いこと、神経症状があること、未充足の必要な支持療法が多いことが、健康関連QOLの低下と関連していた。登録から12か月間で、痛みや疲労が改善し、未充足の必要な支持療法が満たされると、健康関連QOLは有意に改善した。ECD患者では、他のがん患者と比較しても健康関連QOLが大幅に低下している。症状の緩和と未充足の必要な支持療法への対応によって、ECD患者における健康関連QOLは改善する。
3)「18F-FDG PET/CTによる代謝パラメータ、遺伝子変異、臨床的特徴を統合した、LCH患者の治療効果と予後を評価・予測するための臨床研究」
A clinical study incorporating multimodal (18)F-FDG PET/CT metabolic parameters, genetic markers, and clinical characteristics for the evaluation and prediction of treatment efficacy and prognosis in Langerhans cell histiocytosis.
Huang Z, et al. Front Med (Lausanne). 2025 Sep 3;12:1619967.
【目的】LCHは、病的なランゲルハンス細胞の多臓器浸潤を特徴とする稀なクローン性増殖性疾患であり、臨床像や経過は様々である。標準的な化学療法により生存率は著しく改善しているが、奏効率は低く、再発率は高く、一部の患者では長期後遺症が残るなど、依然としていくつかの課題が残っている。18F-FDG PET/CTによる代謝パラメータ、遺伝子変異、臨床的特徴を統合し、LCH患者の治療効果と予後を評価・予測することを目的とした。【方法】2016年5月~2024年12月に江西省人民病院核医学科において、組織病理学的にLCHと診断された26例の臨床データと18F-FDG PET/CT画像所見を後方視的に解析した。4つの代謝パラメータ(SUVmax、TLR、MTV、TLG)に加え、遺伝子変異および臨床的特徴(性別、年齢、病型、病期など)も評価した。全例とも、少なくとも1年間、または病勢進行や再発が生じるまで追跡調査された。無増悪生存期間を評価するために、単変量および多変量解析を実施した。【結果】病勢進行または再発した患者は、治療に反応した患者と比較し、SUVmax、TLR、MTV、TLG値が有意に高かった。ROC曲線分析により、疾患寛解を予測するための最適なカットオフ値は、SUVmax=7.5、TLR=5.2、MTV=25.0、TLG=150.0と特定された。SUVmax高値群、MTV高値群、TLG高値群は、低値群に比べ、寛解率が有意に低く、最も顕著な差はMTVとTLGでみられた(p<0.01)。TLGのAUC値は最も高く(0.91)、強力な予測能を示した。臨床医は、MTV≥25.0、TLG≥150.0の場合、再発リスクに注意する必要がある。単変量解析では、リスク臓器浸潤を伴う多臓器型LCH(MS-LCH RO+)、Ann Arbor分類III期、BRAFV600E変異陽性、MTV>25.0、TLG>150.0が、有意な無増悪生存期間(PFS)の低下因子であった(全てp<0.05)。さらに、高SUVmax群、高MTV群、高TLG群は、PFSが有意に短かった。多変量Cox回帰分析では、MTV高値とTLG高値がPFS低下の独立した予測因子であった。BRAFV600E変異は、MS-LCH群、高SUVmax群、高TLG群に多かった。【結論】18F-FDG PET/CTから得られた診断時の代謝パラメータは、LCHにおいて治療反応性と予後を予測するための有望な画像バイオマーカーである。確立された臨床層別化システムとこれらの代謝指標を統合することによって、より包括的な多次元的な予後評価が可能となる。
4)「小児LCHにおけるカテプシンSおよびPD-L1発現、BRAFV600E変異と臨床的関連性」
Expression and clinical correlation of cathepsin S, programmed cell death-1 ligand 1, and BRAFV600E mutation in children with Langerhans cell histiocytosis.
Ni Y, et al. Turk J Pediatr. 2025 Sep 1;67(4):546-558.
【背景】小児LCHにおいて、BRAFV600E変異とPD-L1発現の臨床的関連性が報告されているが、先行研究の結論は一貫していない。カテプシンS発現の上昇は様々ながんと関連していることが報告されている。しかしながら、カテプシンS発現とLCHの関連に関する研究は現時点では存在しない。小児LCHにおいて、PD-L1およびカテプシンS発現、BRAFV600E変異と臨床的関連性を評価することを目的とした。【方法】35の組織検体でddPCRを用いてBRAFV600E変異を解析し、31の組織検体で免疫組織化学染色を用いてカテプシンSとPD-L1の発現を解析した。さらに、これらの結果と、臨床的特徴および予後との関連を解析した。【結果】BRAFV600E変異の頻度は34.3%(12/35例)であった。BRAFV600E変異は年齢2歳以下および中枢神経リスク部位病変と有意に関連していた(それぞれ66.7%、72.7%)。 PD-L1発現は35.5%(11/31例)に認め、皮膚病変(100%、3/3)と有意に関連していた。PD-L1発現とBRAFV600E変異は関連していなかった。BRAFV600E変異およびPD-L1発現は、いずれも病勢進行・再発・6週間の初期治療反応性と有意な関連はなかった。カテプシンSは31例全ての病変組織で発現していた。カテプシンSのHスコア(免疫染色強度)は2歳以下で有意に高かった。カテプシンSは6週間の初期治療反応性・病勢進行・再発、BRAFV600E変異、PD-L1発現と有意な関連はなかった。【結論】LCHではカテプシンSの発現がみられ、その発現強度は発症年齢2歳以下で高かった。BRAFV600E変異、PD-L1、カテプシンS は、LCH の予後に関連していない可能性がある。
5)「播種性黄色腫の治療 - 系統的文献レビュー」
Treatment of Xanthoma disseminatum - a systematic literature review.
Hansen-Abeck I, et al. J Dtsch Dermatol Ges. 2025 Sep;23(9):1061-1069.
播種性黄色腫は、non-LCH組織球症に属する稀な疾患であり、3つの型に分類され、全身病変を伴うこともある。その希少性ゆえに、本疾患に対する標準的な治療ガイドラインは存在せず、日常臨床において治療を困難にしている。系統的文献レビューを実施することにより、過去22年間の治療経験を要約し、様々な治療選択肢の概要を作成することを目的とした。2002年6月26日~2024年6月26日までの期間のPubMed/MEDLINEデータベースを検索し、播種性黄色腫とその治療戦略に関する体系的な文献レビューを実施した。文献検索の結果、38件の論文が見つかり、そのうち19件を本レビューに含んだ。分析対象となった研究における治療法は、免疫抑制療法、細胞増殖抑制療法、脂質低下療法、外科手術、紫外線照射療法、レーザー療法に分類された。クラドリビンを用いた治療が最も多く報告されていた。現在のデータは主に症例報告と症例シリーズに基づいており、本レビューではそれらを要約して提示した。したがって、治療方針の決定の根拠として利用可能である。
6)「小児LCHの病期分類および経過観察における18F-FDG PET/CTスキャンの有用性:CTやMRIとの比較」
Value of 18F-FDG PET/CT Scans in Staging and Follow-Up of Pediatric Langerhans Cell Histiocytosis: Comparison to CT and/or MRI.
Dien Esquivel MF, et al. Children (Basel). 2025 Aug 20;12(8):1089.
【背景・目的】小児LCHにおける18F-FDG PET/CTスキャンの付加価値を、初期病期分類、再発時の評価、治療後の経過観察において、他の画像診断法(CTおよびMRI)と比較することを目的とした。【方法】2007年6月1日~2022年12月8日にLCHと診断され、登録基準を満たした小児を対象とし、後方視的に調査した。18F-FDG PET/CT画像をCTやMRIと比較した。画像検査の一致度を評価するために、クラス間相関係数(ICC)を用いた。p値が0.05未満の場合、統計的に有意と判断した。【結果】39例の小児が18F-FDG PET/CT検査を受けた。診察時の年齢は中央値10歳(範囲:1.3~17歳)で、女性と男性の比は0.7:1であった。18F-FDG PET/CTと他の画像検査の所見はほとんど一致した(ICC=1, p<0.0001)。初期病期分類でのFDG集積陽性病変のSUVmaxは中央値2.7(範囲:1.3~16.7)であった。【結論】18F-FDG PET/CTはCTやMRIによる診断を補完することが示されており、初期病期分類、再発時の評価、治療後の経過観察時の評価において、代謝情報も得られるという利点がある。これらの予備的な知見から、さらなる研究が望まれる。
7)「肺LCHは本当に稀な疾患か?:後方視的コホート研究」
Is pulmonary Langerhans cell histiocytosis really rare?: A retrospective cohort study.
Akkurt ES, et al. Medicine (Baltimore). 2025 Aug 8;104(32):e43766.
肺LCHは、原因不明の稀な間質性肺疾患であり、典型的には20歳~40歳代に発症する。特徴的な高解像度CT所見が認めれば、生検が回避される可能性がある。肺LCHの臨床的特徴と画像所見を明らかにすることにより、疾患認知度の向上を目的とした。この単一施設後方視的コホート研究(2016~2024年)は、肺LCHと確定診断された26例を対象とした。人口統計学的情報、喫煙歴、併存疾患、症状、臨床検査値、6分間歩行距離、肺機能検査、一酸化炭素拡散能(DLCO)、高解像度CT所見を評価した。年齢中央値は46歳で、84.6%に喫煙歴があった。咳嗽(46.2%)と呼吸困難(53.8%)が多くみられた。放射線学的所見としては嚢胞と結節が多かった。呼吸困難のある患者では初期のDLCOが低かった(P=0.035)。中央値2.5年間の追跡調査期間中、肺機能検査とDLCO値は安定していた。肺LCHの放射線学的特徴を早期発見し禁煙することは極めて重要である。限界はあるものの、これらの知見は既知の知見を補強するものであり、より大規模な前向き研究の必要性を浮き彫りにしている。
8)「成人LCHにおける性別による肺機能への影響」
Impact of Sex on Lung Function in Adult Langerhans Cell Histiocytosis.
Fabozzi A, et al. Life (Basel). 2025 Aug 7;15(8):1258.
【背景】LCHは、肺病変を伴うことが多い稀な組織球性造血疾患である。LCHにおける性別による差異に関するデータは十分ではないため、LCH患者コホートにおける肺機能の性差を評価することを目的とした。【方法】LCHと診断された成人79例のデータを後方視的に解析した。人口統計学的データ、臨床データ、スパイロメトリーデータを収集し、性別ごとに比較した。連続変数はMann-Whitney検定を用いて、カテゴリ変数はカイ二乗検定を用いて解析した。【結果】79例中、女性が47例(59.5%)、男性が32例(40.5%)であった。女性は男性と比較して、一酸化炭素肺拡散能(DLCO%)、肺胞容積当たり一酸化炭素肺拡散能(DLCO/VA%)が有意に低かった。女性は、25%最大呼気流量(MEF25%)、25-75%努力呼気流量(FEF25-75%)などの小気道指標が低い傾向を示したが、統計学的に有意ではなかった。一方、残気量対全肺容量比(RV/TLC)は女性で有意に高かった。多変量回帰分析の結果、肺病変の同定には、機能パラメータの中でDLCO%が最も高い精度(AUC 0.70)を示した。【結論】女性患者において、小気道病変によるガス交換効率の低下と末梢エアートラッピングの増加の組み合わせが、早期の小気道病変と換気・灌流動態の変化を特徴とする、女性特有の機能的LCH表現型の存在を反映している可能性を示唆しており、これがこれらの患者の診療に寄与する可能性がある。さらに、女性患者において、診断時のDLCO%値による肺病変の有無の予測能は中程度であることから、DLCOは肺病変を有する女性患者の検出に寄与する可能性が示唆されるが、前方視的かつ独立した外部検証なしには確定診断検査とみなすべきではない。
9)「BRAFV600E変異陽性LCHには、TERTプロモーターC228TおよびC250T変異を認めない」
TERT Promoter C228T and C250T Hotspot Mutations Are Absent in BRAF V600E-Positive Langerhans Cell Histiocytosis.
Silva AMD, et al. Cancer Med. 2025 Aug;14(15):e71115.
【背景】様々な悪性腫瘍において、BRAFV600EとTERTプロモーター変異(C228TおよびC250T)の同時発現が、悪性度および予後不良に関連すると報告されている。しかし、LCHにおいてはTERTプロモーター変異については未だ解析されていない。【方法】BRAFV600E変異陽性のLCH検体40例のホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE)からDNAを抽出し、TERTプロモーターC228TおよびC250T変異の有無を解析した。変異スクリーニングには、ネステッドPCR法、サンガーシークエンシング、NGSを併用した手法を用いた。【結果】解析対象検体におけるBRAFV600Eの変異アレル頻度(VAF)は、中央値17%(幅:0.1%~33.6%)であった。LCH検体40例中33例が解析可能であったが、全例でTERT C228TおよびC250T変異を認めなかった。【結論】BRAFV600E変異陽性LCHには、TERTプロモーターC228TおよびC250Tのホットスポット変異がないことが示された。これは、TERT プロモーター変異が LCH の発症に重要な役割を果たしていない可能性を示唆している。
10)「成人の脊椎LCH:まれで論争の的となる疾患:系統的レビュー。」
Langerhans cell histiocytosis of the spine in adults: A rare and controversial disorder: A systematic review.
Abdulla E, et al. Clin Neurol Neurosurg. 2025 Aug;255:108991.
【はじめに】成人の脊椎LCHはまれである。治療せずに放置すると、進行性の神経障害や脊椎不安定性を引き起こす可能性がある。小児においては多くの報告があるが、成人における病態、治療、転帰については十分に解明されていない。これまでに報告された成人脊椎LCHに関する包括的な文献レビューを提示する。【目的】成人における脊椎LCHの診療における転帰と臨床経験を提示する。【方法】オンラインデータベースを検索し、報告された成人脊椎LCH症例の系統的レビューを実施した。【結果】47例が見出された。男性が63.8%であった。平均発症年齢は34.7歳(範囲:20~69歳)であった。最も多くみられた症状は、局所痛、放散痛、運動制限であった。最も頻度の高い病変は腰椎であった。椎体病変のある例は53.2%で、扁平椎はわずか3例であった。42例(89.4%)は単一椎体に限局し、5例(10.6%)は複数の椎体に病変がみられた。最も顕著な放射線学的所見は椎体の溶解性破壊であった。29例が手術を受け、前方除圧、後方除圧、複合除圧、その他の術式が行われていた。平均追跡期間は22か月(範囲:1~120か月)であった。再発または病勢進行がみられた7例を除き、転帰は全例で良好から極めて良好であった。【結論】外科的介入は、神経学的問題または脊椎不安定性を示す成人患者に有効であるように思われる。小児では非外科的治療が一般的であるが、病勢進行や再発が多く、個別化された治療計画が必要性である。