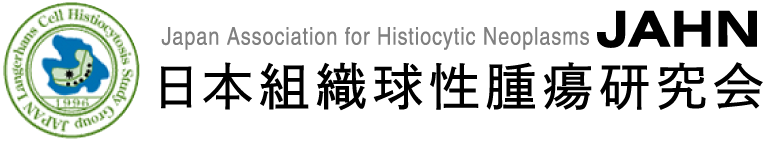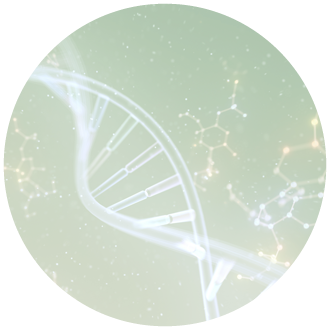最新学術情報
第72回 最新学術情報
1)「小児におけるランゲルハンス細胞組織球症の脊椎病変の治療:系統的レビュー」
Management of Spinal Langerhans Cell Histiocytosis in Children: A Systematic Review.
Subramaniam MH, et al. Int J Spine Surg. 2024 Nov 19;18(6):769-80.
【背景】LCHの脊椎病変は、小児では単一臓器型孤発型のこともあるし多臓器型の一病変のこともある。単一臓器孤発型の治療法は多岐にわたる。病変の自然治癒を待ち経過観察、病変へのステロイド注射、全身化学療法、放射線療法、手術などが選択肢となる。治療選択肢が多数あるため、治療方針の選択は専門医によって難題である。GargのX線椎体崩壊度分類に基づいて、LCHの脊椎病変の診療アルゴリズムの構築を試みた。【患者と方法】体系的レビューおよびメタアナリシスの推奨報告項目2020ガイドラインに従い、既存の医療データベースから文献を抽出した。2003年から2022年の間に発表された文献を、厳格な包含基準と除外基準を用いて絞り込んだ。筆頭および第二著者は、抽出した文献の要約をレビューした。本研究は Prospero に登録した。含められた文献のバイアス評価は、MINORの基準を使用して評価した。【結果】8つの後方視的な症例シリーズが選定された。これらの研究では、計 116例の小児(平均年齢 7.4歳)が治療を受けていた。平均追跡期間は 52.1か月であった。これらの患者の病変の内訳は、頸椎37個、胸椎40個、腰椎25個、仙骨1個であった。全身化学療法は、放射線画像上の椎体崩壊のリスクを軽減していた (p<0.05)。手術は、GargのグレードIB、II の病変に対しては手術が有効で、椎体高を回復させていた(p<0.05)。グレードIII に関する症例シリーズはなかった。病変の最終目標すなわち治癒を示す重要な放射線学的パラメータである椎体高の再建は、手術によって最も早くに達成され、続いて全身化学療法、装具、経過観察の順で合った。【結論】GargのグレードIAでは経過観察が望ましい。グレードIB およびIIの病変は手術が有効な選択肢である。グレードIIIの病変の治療は、個別に治療法を検討する必要がある。
2)「小児LCHの病変検出のための循環腫瘍DNAと画像解析の組み合わせ」
Circulating Tumor DNA Combining with Imaging Analysis for Lesion Detection of Langerhans Cell Histiocytosis in Children.
Liu S, et al. Children (Basel). 2024 Nov 27;11(12):1449.
【背景】循環腫瘍DNA(ctDNA)からの変異の検出は、有望な強化技術である。この後方視的研究では、最初にLCHの病勢評価におけるctDNAと画像の重要性を分析し、さらにLCHの病勢評価におけるctDNAのより広範な役割を解析した。【方法】データ視覚化および生存分析モデルを用いて、cfBRAFV600E値による治療反応評価および放射線学的反応評価が臨床転帰と一致するかを検討した。次に、cfBRAFV600E値による治療反応評価を動的観点から分析した。その後、cfBRAFV600Eと病変組織BRAFV600E変異の状態を比較検討し、LCHの臨床症状および予後との関係を分析した。【結果】2019年~2023年の間に119例がこの試験に登録された。放射線学的とcfDNAの両方で疾患進行と評価された例は、そうでない例と比較して、無増悪生存期間(PFS)は有意に短かった(17.67か月 vs. 24.67か月, p<0.05)。cfBRAFV600E陽性と判定する重要なカットオフ値は0.03%と初めて決定された。cfBRAFV600Eおよび病変組織BRAFV600Eの両方が陽性の例は、3 歳未満の子どもに多く、皮膚および脾臓の病変があり、3年PFS率が低かった。病変組織BRAFV600Eとは対照的に、cfBRAFV600E陽性例は陰性例に比べ、リスク臓器浸潤LCHの割合が高く(52.0% vs. 27.9%, p<0.05)、6週目での治療反応は良好であった(24.0% vs. 4.7%, p<0.05)。さらに、リスク臓器浸潤 LCH および多臓器LCHでは、cfBRAFV600E陽性例は3年PFSが有意に低かった。【結論】これらの知見は、小児LCHにおけるctDNAおよび画像分析の適用意義を強化、補足する。
3)「共通の前駆細胞を起源とするRosai-Dorfman病と明細胞肉腫」
Common progenitor origin for Rosai-Dorfman disease and clear cell sarcoma.
Sato A, et al. J Pathol. 2024 Nov;264(3):243-249.
成人の組織球性腫瘍は、血液悪性腫瘍や固形悪性腫瘍を高頻度に合併すると報告されている。組織球性腫瘍と血液悪性腫瘍が共存する場合には、一部の例で同じ遺伝子変異を共有するとの報告があるが、組織球性腫瘍と固形悪性腫瘍の間では遺伝子変異が共通している報告はほとんどない。明細胞肉腫 (CCS) を合併した Rosai-Dorfman 病 (RDD) の症例を報告する。RDDは稀な組織球性腫瘍である。CCSは非常に稀な予後不良の軟部肉腫である。全エクソン変異解析により、NRAS G12SおよびTP53 c.559+1G>Aを含む6つの共通した体細胞変異が、RDDとCCSの両者の組織で検出された。これは、RDDと固形悪性腫瘍とのクローン関連性を遺伝子解析により示した初めての報告である。CCSの起源である神経堤細胞がRDDとCCSの共通の起源細胞である可能性が高いと推定した。この症例は、組織球性腫瘍において固形悪性腫瘍が共存することがなぜ多いのかを臨床病理学的に解明するのに役立つ。
4)「不定型樹状細胞組織球症はLCHとは異なり、他の造血器腫瘍を併発することが多い」
Indeterminate DC histiocytosis is distinct from LCH and often associated with other hematopoietic neoplasms.
Ozkaya N, et al. Blood Adv. 2024 Nov 26;8(22):5796-5805.
不確定樹状細胞組織球症 (IDCH) は、LCHと同様にCD1a陽性/S100陽性であるが、 ランゲリン(CD207)の発現は低下または欠損している組織球の蓄積を特徴とする稀な疾患である。43 例のIDCH(CD1a陽性/CD207<20%の免疫表現型によって定義)の臨床所見、病理学的所見、遺伝子変異を解析した。発症時年齢は中央値70歳(IQR:44~80歳)で、皮膚病変(31/43例; 72%)とリンパ節病変(11/43例; 26%)が多かった。18/43例(42%)が組織球性以外の造血器腫瘍(「続発性」IDCH)を、7/43例(16%)がIDCH以外の組織球症(「混合型」組織球症)を合併していた。ほとんどの症例は、形態学的にLCHと鑑別できなかったが、CD1c陽性/CSF1R(CD115)陰性で、正常な不確定細胞および古典的樹状細胞タイプ2の特徴を示した。遺伝子変異解析により、高頻度なKRAS 変異(13/32例; 41%)とBRAF V600E変異(11/36例、31%)の存在が明らかになり、ほぼ相互排他的であった。RNAseq分析により、6例において、唯一の遺伝子変異としてETV3::NCOA2融合を認めたが、これらの例には他の組織球症や造血器腫瘍の併発はなかった。BRAF変異/MAP2K1変異は、ランゲリン発現が部分的に保持(1~20%)されていること(P=0.005)、混合組織球症であること(P=0.002)と有意に関連していた。注目すべきことに、数例のIDCH組織において、組織球症でよくみられる遺伝子変異に加え、骨髄性腫瘍によくみられる遺伝子(DNMT3A、TET2、SRSF2)の変異を認めた。4例においてIDCHおよび合併しているIDCH以外の造血器腫瘍の両者の遺伝子変異を解析したところ、共通した変異を認めた。診断時年齢および診断時のリンパ節病変が全生存率の低下と関連していたが、BRAF / RAS 経路の遺伝子変異は転帰に影響していなかった。これらの結果は、IDCHの診断評価、分類、治療管理に役立つ。
5)「Erdheim-Chester病における中枢神経系病変:磁気共鳴画像検査」
Central nervous system involvement in Erdheim-Chester disease: a magnetic resonance imaging study.
Zahergivar A, et al. Clin Imaging. 2024 Nov;115:110281.
【目的】58例のErdheim-Chester病(ECD)のコホートにおいて脳MR画像所見の特徴を明らかにし、これらの所見とBRAFV600E変異との関連を評価する。【方法】生検でECDと確認された、性別および民族を問わない2~80歳のECD患者を対象とした。ECDの 中枢神経(CNS)病変の活動性の評価に経験のある2名の放射線科医が MRI 検査を読影した。意見が分かれた場合3人目の読影者が判定した。CNS病変の頻度を分析した。CNS 病変の分布と BRAFV600E変異との関連性は、フィッシャーの正確検定とオッズ比を用いて評価した。【結果】58例、全てで、脳MRI画像で、おそらくECDによると思われる何らかのCNS病変が明らかとなった。皮質病変を27例(46.6%)に、小脳病変を15例(25.9%)に、脳幹病変を17例(29.3%)に、下垂体病変を10例(17.2%)に認めた。早期の皮質萎縮を8例(13.8%)に認めた。BRAFV600E変異は、小脳病変(p=0.016)と両側脳幹病変(p=0.043)と有意に関連していた。脳萎縮については有意な傾向(p=0.053)が認められた。【結論】この研究により、ECDにおける脳MRI所見、それらとBRAFV600E変異、特に両側性病変を伴う例における関連について貴重な知見が得られた。ECDがどのように脳構造に影響を及ぼすかについて理解が深まっている。MRI検査でのCNS病変パターンと BRAF などの遺伝子変異との関連に関する知識は、予後予測と診療方針の両方に役立つ。
6)「成人LCHにおける消化管病変の症状と転帰」
Manifestations and outcomes of digestive tract involvement in adult Langerhans cell histiocytosis.
Shang Q, et al. Ann Hematol. 2024 Nov;103(11):4459-4466.
LCHは、ランゲルハンス細胞の増殖を特徴とする幅広い臨床像を呈する組織球症である。LCH における消化管病変は、頻度は低いが、その臨床像は依然としてほとんど明らかにされていない。465例の単一施設のコホートにおいて、LCHの消化管病変(LCH-GI)が病理学的に確認された成人13例を対象として、年齢・性別、臨床所見、内視鏡所見、遺伝子変異、追跡調査の結果を後方視的に分析した。LCH-GIを認めたのは2.8%であった。LCH-GIと診断された時点で、7例(53.8%)は孤発病変で、6例(46.2%)は多臓器病変があった。LCH-GI 発症時、6例(46.2%)は胃腸症状がなかったが、他の例には胃腸症状があった。最も多い病変部位は胃(61.5%)、次いで食道(23.1%)、結腸(7.7%)、肛門(7.7%)であった。内視鏡検査が行われた12例の所見は様々で、8例(66.7%)に粘膜下隆起性病変、4例(33.3%)に糜爛・粗い顆粒状粘膜・局所的色調異常などの非隆起性病変を認めた。遺伝子変異検査を受けた8例中5例(62.5%)にBRAFV600E変異が検出された。無増悪生存率の推定値は 91.7%であった。内視鏡検査で粘膜下腫瘤が認められた患者の無増悪生存率は、腫瘤病変のない患者よりも有意に良好であった。この研究では、消化管病変を伴う13 例のLCHを報告した。LCHの早期発見のためには、内視鏡検査を行い粘膜下隆起や糜爛などの病変を生検し病理学的に検査することが重要性である。診療には、包括的な全身評価と定期的な内視鏡モニタリングが不可欠である。治療は経過観察中に臨機応変に個別化する必要がある。
7)「成人のRosai-Dorfman-Destombes病:単一施設での経験」
Rosai-Dorfman-Destombes disease in adults: a single center experience.
Leung E, et al. Ann Hematol. 2024 Nov;103(11):4467-4476.
Rosai-Dorfman-Destombes病(RDD)は、最近の医療の進歩、特に遺伝子変異解析、分子標的療法、PET-CT画像検査の進歩により、認識が深まり転帰の改善が期待されている。この研究では、限られた医療資源の活用を考慮しなければならない「現実世界」の環境において診断・治療を受ける患者について記述する。2015年11 月~2023年10月までにバンクーバー総合病院の単一施設でRDDと診断された成人15例を後方視的に解析した。年齢の中央値は 53 歳で、男性5例、女性10例であった。 15例の全てにリンパ節外病変を認め、11例はリンパ節外病変のみ、4例はリンパ節病変も伴っていた。7例に次世代シーケンス(NGS)による病変の解析が行われ、4例にMAP2K1変異を認め、1例はKRAS p.K117N変異が同定されトラメチニブを用いた分子標的療法を受けた。4 例では、病期分類にPET-CTが用いられた。難治性の6例はレナリドミドとデキサメタゾンにより治療され、重大な毒性なく経過し、3例は完全奏効し、3例は部分奏効であった。RDDでは様々な結節外症状があることが明らかとなった。レナリドミドとデキサメタゾンの併用は、一部の患者、特に難治性の例に対して効果的で忍容性の高い治療選択肢である。NGSとPET-CTの幅広い活用は、治療方針の判断に有用である。
8)「Non-LCHにおける腎病変の臨床像と転帰」
Clinical Spectrum and Outcome of Kidney Involvement in Non-Langerhans Histiocytosis.
Miao HL, et al. Kidney Int Rep. 2024 Oct 10;10(1):209-216..
【はじめに】腎病変を伴うRosai-Dorfman病 (RDD) とErdheim-Chester 病 (ECD) の臨床的特徴と治療反応を明らかにすることを目的とした。【方法】2005年~2023年に経験した腎病変を伴うRDDおよびECD症例を後方視的に分析し、腎機能の変化、CTとPET-CTにより治療反応性を評価した。【結果】RDD 4例とECD 44例が対象となり、年齢中央値はそれぞれ58歳と51歳であった。RDD患者には腎病変に伴う症状はなかったが、ECD患者は27.3%に下肢浮腫を認めた。推定糸球体濾過量(eGFR)の中央値は、RDDで80.5(63‐125)、ECDでは100(22‐133)ml/分/1.73 m2 であった。RDD患者は全例に腎腫瘤を認め、ECD患者の68.2%に腎周囲浸潤を認めた。RDDの2例がステロイド(1例は腎摘出後)投与を、2例がレナリドミド/デキサメタゾン(RD)療法を受けた。RDDの1例(25%)がeGFRの改善を認め、3例(75%)がCTおよびPET-CTで改善を認めた。ECD 34例のうち、26例がインターフェロンα、5例がBRAF阻害剤、3例がシタラビンで治療された。eGFR改善率、CT反応率、PET-CT反応率はそれぞれ14.7%、5.9%、52.9%であった。追跡期間の中央値は、RDDで27.0か月、ECDでは53.0か月であった。5 年生存率は、RDDで66.7%、ECDで81.8%であった。無増悪生存率の中央値は、RDDで18.3か月、ECDで59.4か月であった。【結論】RDDとECD における腎病変の特徴と治療反応を詳細に示し、RDDでは腎腫瘤、ECDでは腎周囲軟部組織が典型的であった。ECD患者は不可逆的な腎機能障害をきたす可能性があり、早期診断と時期を逸しない治療が極めて重要である。
9)「眼窩のLCH:228例の系統的レビュー」
Orbital Langerhans Cell Histiocytosis: A Systematic Review of 228 Cases.
Al-Wassiti AS, et al. Cureus. 2024 Oct 8;16(10):e71059.
眼窩LCHは非常にまれな疾患であり、症状が多岐にわたり、診断が困難であることがしばしばある。眼瞼腫脹や眼球突出などの一般的な症状から、頭痛や複視などの非常に非定型的な症状まで、さまざまであるため、診断の遅れや誤診が生じやすい。この系統的レビューでは、眼窩 LCH の臨床症状、診断アプローチ、治療法、転帰を詳細に記述することを目的とした。系統的レビューはPRISMAガイドラインに従って実施した。2024 年 8 月までの文献を PubMed と Scopusで検索がした。18 件の論文から 228 例のデータが得られた。研究デザイン、症例数、患者の年齢・性別・民族、臨床症状、診断基準、治療法、観察期間、再発率、合併症に関するデータを抽出した。眼窩LCH患者の平均年齢は8.5歳(SD±7.1歳)と若年者に多く、男性が152例(66.7%)、女性が76例(33.3%)であった。最も多かった症状は眼瞼腫脹で108例(47.4%)に認め、多くの場合、診断の契機となる初発症状であり、眼球突出を95例(41.7%)に認め、より重大な眼窩病変を示唆し、触知可能な腫瘤を80例(35.1%)に認めた。画像診断は診断において重要な役割を果たし、CT または MRI によりほぼ全ての症例 (99%) で溶骨性病変が描出された。病理組織ではCD1a および S-100蛋白が LCH の特徴的なマーカーであることが確認された。眼窩 LCH の治療戦略は、疾患の程度、患者の特徴、施設によって様々であった。外科療法は最も多く用いられた治療法で136 例(59.6%)が受けており、局所病変に対しては非常に効果的であった。放射線療法は68例(29.8%)に行われ、多くの場合、手術の補助療法、または、残存病変や切除不能病変に対する一次治療として行われていた。化学療法は85例(37.3%)に施行され、特に多臓器型の例で多かった。少数例、特に孤発性または無症候性の例では、自然治癒の可能性を考慮して無治療経過観察されていた。寛解率は79.8%と高かったが、14.9%が再発したことから、綿密な追跡調査が必要と考えられた。中枢性尿崩症を合併する例があり、多臓器型の兆候であった。眼窩LCHは、正確な診断と効果的な管理のために多分野にわたるアプローチを必要とし、高度な画像診断と分子マーカーに基づいた個別治療が必要である。再発率を低下させるためには、治療プロトコルを改良するためのさらなる研究が必要である。
10)「オランダとベルギーにおける組織球性腫瘍に対する分子標的療法の実臨床経験」
Real-world experience with targeted therapy in patients with histiocytic neoplasms in the Netherlands and in Belgium
Paul G, et al. Blood Neoplasia. 2024; 1: 100023.
組織球性腫瘍は、MAPKシグナル伝達経路への著しい依存を特徴とする稀な造血腫瘍である。分子標的療法は新たな治療選択肢となっているが、報告されている患者数は依然として限られている。本稿では、オランダとベルギーの7つの三次医療機関において分子標的療法を受けた組織球性腫瘍40例について報告する。このコホートは、小児6例(15%)と成人34例(85%)からなり、LCH(12例)、Erdheim-Chester病(14例)、中枢神経系黄色肉芽腫(2例)、Rosai-Dorfman病(3例)、組織球性肉腫(2例)、ALK陽性組織球症(1例)、混合型/分類不能型組織球性腫瘍(6例)と様々な組織球性腫瘍が含まれていた。5例が臨床試験に組み入れられ、35例(88%)が試験外でBRAF/MEK阻害剤の投与を受けた。追跡調査データが得られた35例の分子標的療法の治療期間は中央値1.9年(範囲:0.04~5.8年)であった。多臓器病変および/または腫瘤性病変に対して治療を受けた27例中25例(93%)、および、神経変性LCHに対し治療を受けた8例中2例(25%)に完全奏効または部分奏効を認めた。奏効は概ね持続的でしたが、10例は用量減量または治療中断に伴い増悪した。10例中9例で再び奏効が得られた。2例が新規または進行性の神経変性病変を発症し、1例はベムラフェニブ治療中、もう1例はベムラフェニブ治療後であった。最終追跡調査では、8例の成人患者が毒性のために分子標的療法を中止していた。本研究は、これまでに報告されている組織球性腫瘍に対するBRAF/MEK阻害薬による治療の良好な転帰を裏付けている。しかし、限界も浮き彫りにしており、前向き研究の必要性が示唆される。