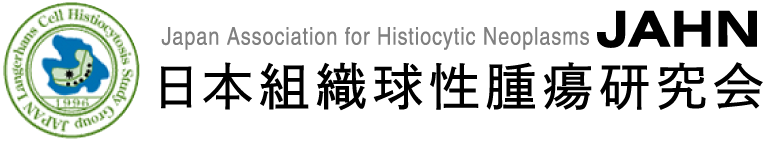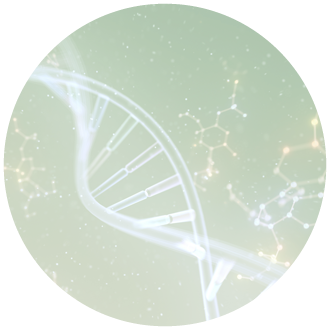最新学術情報
第73回 最新学術情報
1)「成人LCH患者においてBRAF欠失は、多臓器型および予後不良と関連する」
BRAF deletion in adult patients with Langerhans cell histiocytosis correlates with multisystem disease and poor outcome.
Lang M, et al. Clin Cancer Res. 2025 Jan 6;31(1):197-204.
【背景】LCHは、まれで非常に多様性のある組織球症である。現在、LCH の成人患者における分子プロファイリングと臨床所見や転帰との関連を調べた研究はほとんどない。成人 LCH の遺伝子変異の特徴を明らかにし、遺伝子変異と臨床的特徴や転帰との関連を見出すことを目的とした。【方法】2000年1月~2023年12月までに組織学的にLCHと診断された18歳以上の254例を対象とした。全例に次世代シーケンシング(NGS)解析またはBRAFV600E変異の蛍光定量PCR(qPCR)を行った。患者の年齢/性別、臨床所見、治療について電子カルテを通じて収集した。患者の転帰は、電子カルテまたは電話インタビユーによって収集した。【結果】全体で254例が登録された。77.6%(197例)にMAPK/PI3K経路の遺伝子変異を認めた。BRAFV600E変異が最も多く(30.7%、78例)、次いでBRAF indel(18.1%、46例)、MAP2K1変異(12.6%、32例)であった。 BRAF indelは、単一臓器型に比べ多臓器型に有意に多かった (24.5% vs. 6.6%、p<0.001)。患者全体では、BRAFindel は全生存率 (3年OS 89.6% vs. 99.0%、p=0.014) 、無増悪生存率 (3年PFS 50.0% vs. 78.6%、p<0.001) ともに低かった。多臓器型に限っても、BRAFindel のPFSは低かった(3年PFS 47.8% vs. 76.0%、p=0.001)。【結論】この大規模研究は、成人 LCH の遺伝子変異および臨床病理学的特徴を示している。BRAFindel は多臓器型に多く、予後不良であった。
2)「成人の胃の孤発性LCH:臨床病理学的特徴と分子遺伝学の分析」
Isolated Langerhans cell histiocytosis of the stomach in adults: An analysis of clinicopathologic characteristics and molecular genetics.
Wu R, et al. Medicine (Baltimore). 2024 Dec 20;103(51):e40950.
孤発性胃LCHは、成人には非常にまれである。このまれな疾患の臨床病理学像および遺伝子変異を特徴づけた。過去10年間に孤発性胃LCHを発症した3例と、文献からの20例をレビューして、臨床病理学的特徴および予後を後方視的に分析した。孤発性胃LCHの23例を対象とした。男性15例、女性8例で、年齢は平均44.5歳(中央値48歳、範囲21~68歳)であった。胃の不快感と腹痛が最も多い主症状であった。病変は主に胃体部と幽門に集中していた(21/23例)。胃内視鏡検査では隆起性病変/ポリープが多かった。遺伝子解析では、BRAFV600E変異が10/11例(42%)で確認された、KRAS変異は見られなかった(0/5例)。23例のうち、内視鏡以上の治療を受けた例はなかった。20例で追跡調査(4~66か月)がされた。非典型的な形態学的特徴を示した1例は、腫瘍の摘除から2か月後に原因不明で死亡した。1例は、頭蓋骨と腋窩部に病変が出現した。残りの18例は、追跡期間中に疾患進行はなく生存した。胃内視鏡生検による日常の診断において、胃体部または幽門部の隆起性病変/ポリープで組織学的に重度の炎症が明らかになった場合、LCHの可能性を考慮する必要がある。さらに、組織学的に腫瘍細胞様の核小体や有糸分裂像、壊死を認める場合、悪性転化を伴うLCHの可能性に注意する必要がある。免疫組織化学マーカーCD56は、形態の判定が困難な場合にLCHとランゲルハンス細胞肉腫を区別するのに役立つ可能性がある。遺伝子解析では、胃LCHにおいてBRAFV600E変異が検索された例の90.9%が変異陽性であったが、症例数が少ないため、さらなる研究が必要である。このデータは、成人における孤発性胃LCHの予後が良好であることを示しているが、早期に疾患進行や全身性病変を見出すために長期にわたる追跡調査が必要である。
3)「小児LCHにおけるBRAFV600E変異以外の遺伝子変異と臨床像との関連」
Beyond BRAF(V600E): Investigating the Clinical and Genetic Spectrum of Langerhans Cell Histiocytosis in Children.
Tang X, et al. Cancer Med. 2024 Dec;13(24):e70532.
【背景】LCHは、小児で最も多い組織球性腫瘍であり、臨床症状は非常に多彩である。現在、小児LCHにおいて、BRAFV600E変異以外の遺伝子変異と臨床像との関連は十分に解明されていない。【方法】本研究では、当センターで治療を受け、BRAFV600E変異以外の遺伝子変異をもつ33例の小児LCHに関するデータを提示した。さらに、2010年1月~2024年8月に報告された BRAFV600E以外の遺伝子変異をもつ小児 LCH 症例を包括的に検討した。【結果】BRAFV600E以外の遺伝子変異をもつ小児 LCH 309例が見出され、そのうち33例が当センターの患者であった。これらのLCH症例に、49 種類のMAP2K1変異、31種類のBRAF変異、4種類のARAF変異を認めた。当センターでは、リスク臓器病変を伴う多臓器型LCHの2例 (いずれもBRAF 486_P490del変異) が6週間の寛解導入療法に対し反応不良であった。MAP2K1または他のBRAF変異のある303例のうち、MAP2K1変異の例は、BRAF変異の例よりも骨単独型(SS-bone)が多かった(p=0.0072)。MAP2K1変異のある例の中では、エクソン3変異はエクソン2変異よりも SS-boneが多かった(p=0.042)。さらに、BRAFエクソン15変異の例は、BRAFエクソン12変異の例に比べ、MAP2K1エクソン2変異の例はMAP2K1エクソン3変異の例に比べ、発症年齢が3歳未満の例が多かった(p=0.037, p=0.0015)。BRAFエクソン15変異のある例は、BRAFエクソン12変異のある例と比較して、肝臓病変が多かった(p=0.042)。【結論】小児LCH患者では、MAP2K1およびBRAF遺伝子にしばしば体細胞変異を認め、各変異は臨床症状と関連している。
4)「補助生殖医療で生まれた子どもにおけるLCH」
Langerhans cell histiocytosis in children born after assisted reproductive technology.
Williams CL, et al. Reprod Biomed Online. 2024 Dec;49(6):104379.
【研究命題】補助生殖医療 (ART)により生まれた子どもは、LCHを発症するリスクが高いか? 【方法】英国ヒト受精・胚機構により記録されたARTで生まれた子どものデータと国立小児腫瘍登録簿のデータをリンクし、LCHを発症した子どもの数を判定した。ARTで生まれた子どもにおける、同じ暦年で同じ年齢と性別の一般人口と同じ発生率を示した場合の予想発症数を導き出すため、一般人口のLCH発症率と組み合わせて、リスク人年を用い計算した。標準化発症率比 (SIR) は、観察された症例数と予想される症例数の比率として導き出した。正確な 95% CI を計算した。【結果】ARTによりに生まれた子どもは計118,155 人で、796,633人年追跡調査した(平均追跡期間 6.74年)。ARTコホートで8例のLCH発症が確認されたが、予想症例数は3.75であった(SIR 2.135, 95%CI 0.92-4.21, P=0.074)。卵細胞質内精子注入法(ICSI)(SIR 4.02, 95%CI 1.31-9.39)および男性因子不妊(SIR 5.41, 95%CI 1.47-13.84)に関連する例が有意に多かった。症例のほとんど(6例)は単一臓器型であった。【結論】この研究では、ICSIで生まれた子どもと、男性因子不妊の父親を持つ子どもで、LCH 発症が有意に多かった。ARTで生まれた子どもは、有意ではなかったがLCH発症率が高かった。過剰リスクの絶対値は小さかった。LCH発症は希であること、この大規模コホートに含まれる症例数が少ないことを考慮すると、ARTで生まれた子どものLCH発症リスクに関してさらなる研究が必要である。
5)「乳房の節外Rosai-Dorfman病:1969年から2023年までの文献レビュー」
Extranodal Rosai-Dorfman disease in the breast: a literature review from 1969 to 2023.
Haro-Cruz JS, et al. Cir Cir. 2024;92(6):741-750.
【目的】乳房の節外性Rosai-Dorfman病に関する文献をレビューし、この疾患の臨床的特徴、治療法、転帰について分析する。【方法】2024年1月に、PubMed、SpringerOpen、Scopus データベースを「Rosai」、「Dorfman」、「Breast」というキーワードで検索した。最終分析には 42報の論文が含まれ、乳房に病変のある節外性Rosai-Dorfman病の報告は計70例であった。患者の特徴、マンモグラム所見、治療管理、転帰を分析した。【結果】患者は主に 60 代の女性(93%)で、硬くて圧痛のない結節(65.7%)を呈し、通常は片方の乳房に限局(72%)していた。約18.6%の患者に他の節性または節外性病変を認めた。切除生検が主な治療戦略(63%)であり、外科的切除は切開生検よりも再発率が低かった(p=0.049)。疾患の再発や進行は、ほとんどが最初の2年以内に生じていた。【結論】この研究では、外科的切除は待機的管理よりも再発または進行する率が低いことが明らかになった。再発は 2 年以内に局所的に発生する傾向があるため、マンモグラフィーと身体診察で経過観察が可能である。
6)「LCH患者において、末梢血中単球数は治療後に大幅に減少し、病変を反映している可能性がある」
Circulating monocytes decrease significantly following disease-directed therapy and may reflect disease expansion in Langerhans Cell Histiocytosis.
Ali H, et al. Ann Hematol. 2024 Dec;103(12):5123-5144.
相対的単球増多と肺LCHの再発との関連を調べることを目的とした。20年間で経験した組織病理学的に診断された86例のLCHの臨床所見、検査所見、画像所見、治療内容のデータを収集した。性別、診断時の年齢、診断までの時間、分子診断データ、画像データを分析した。治療反応は主に画像所見によって評価し、MRIやCTスキャンには RECIST 1.1 基準を、連続 PET 画像には PERCIST基準を用いた。診断時と直近の値を含むさまざまな時点での末梢血単球絶対数も評価した。末梢血中の単球数の絶対値は、診断時と直近の値の間で差はなかったが、病変進行時(平均値 0.94 K/μL)は治療再開後(平均値 031 K/μL)よりも有意に高かった(p=0.000794)。LCHの病変進行時における相対的な単球数増加は、病変進行に伴う末梢血中LCH細胞の増加やMHCクラス1の発現上昇に伴う成熟樹状細胞への分化による単球産生の増加に関連している可能性がある。この傾向は、組織障害や環境要因による刺激によって誘発される肺LCHで特に顕著であった。この現象は、Rosai-Dorfman病やErdheim-Chester病といったnon-LCHでこれまで我々が見出した所見に一致していた。LCH の分子的基礎をさらに解明し、この単球増加の病因を探るために、LCH の分子特性を評価し最終的にこの単球増加の起源を明らかにするための拡張統合ゲノムトランスクリプトーム配列解析が進行中である。これらの研究により、特に単球のシグナル伝達と分化に関連するLCHの根底にある分子機構について貴重な洞察が得られるであろう。
7)「小児LCHの臨床的特徴と生存率:中所得国 (mic) の全国多施設研究」
Overall manifestations and survival of pediatric patients with Langerhans cell histiocytosis. A middle-income country (mic) national multicenter study.
Velasco-Hidalgo L, et al. Bol Med Hosp Infant Mex. 2024;81(6):328-336.
【背景】LCHは、樹状細胞のクローン性増殖を特徴とする稀な腫瘍性疾患である。メキシコでは18 歳未満で9番目に多い腫瘍である。この研究は、2010年1月~2018年12月までにLCHと診断され治療を受けたメキシコの小児の臨床的特徴・治療・生存率を明らかにすることを目的とした。【方法】メキシコの認定病院19施設のデータを用いて後方視的に解析した。2010年1月~2018年12月までにLCHと診断された18歳未満の253例を対象とした。【結果】全例が組織病理学的診断を受け、各治療施設で経過観察された。診断時年齢は中央値19か月であった。最も多い病変部位は骨(178例、70%)と皮膚(131例、70%)であった。リスク臓器陽性群のうち、48例(42%)に造血器病変、62例(53%)に脾腫、39例(34.8%)に肝病変を認めた。化学療法を受けた例のうち、61.2%が完全奏功したが、36例(14.2%)が寛解後に再発した。最も多い再発部位は、皮膚、骨、リンパ節、肝臓であった。全生存率は91.3%で、リスク臓器陽性群(77%)は、リスク臓器陰性群(97%)、および、中枢神経または脊髄病変陽性群(100%)と比較して有意に低かった(p=0.001)。【結論】今回の報告は、メキシコの小児LCHを対象に実施された多施設研究の結果を実証することを目的としており、比較的頻度の低い疾患に対するこれらの治療結果はさらなる研究に値する。
8)「皮膚外病変のある若年性黄色肉芽腫におけるCLTC::SYK融合とCSF1R変異の再現性」
Recurrent CLTC::SYK fusions and CSF1R mutations in juvenile xanthogranuloma of soft tissue.
Kemps PG, et al. Blood. 2024 Dec 5;144(23):2439-2455.
若年性黄色肉芽腫(JXG)は、通常は皮膚病変を呈する組織球性腫瘍である。まれに皮膚外病変を呈するが、皮膚外病変を呈するJXGの遺伝子変異はまだ完全には解明されていない。16例の皮膚外病変を呈する小児のJXGと5例の中枢神経病変または軟部組織病変を呈する成人の黄色肉芽腫の、臨床所見と遺伝子変異について報告する。組織検体はオランダ全国病理学データバンクを通じて入手し、小さなゲノム変異と遺伝子再構成の両者を検出できる革新的な配列決定技術により分析した。分子標的療法の対象となるキナーゼ遺伝子の変異が、小児では16例中16例に、成人では5例中1例に検出された。6例の小児にCLTC::SYK融合、7例の小児にCSF1R変異を認め、いずれも2歳未満であった。1例はCSF1R変異とMRC1::PDGFRB融合が合わさっていた。ほとんどは外科的に治療されたが、CLTC::SYKの6例中1例とCSF1R変異の7例中2例が自然退縮し、このことは全例に治療が必要であるわけではないことを示している。CLTC::SYK融合の例の多くはTouton型巨細胞を認めなかったが、他の多くのJXGの組織学的特徴を示し、メチル化プロファイルに違いはなかった。多重免疫蛍光を用いた解析では、脾臓の細胞において、リン酸化チロシンキナーゼの発現は CD163陽性組織球に局在しており、CLTC::SYK 融合の腫瘍でもmTOR活性化、サイクリンD1発現、さまざまな程度のERKリン酸化を示した。BRAFV600E変異は、小児1例と中枢神経病変のある成人1例で検出され、2例ともBRAF阻害に反応した。最後に、TPM3::NTRK1融合とMAP2K1欠失が自然退縮した小児の全身性JXGで1例ずつ検出された。本研究は、組織球性腫瘍の分子的理解を促進し、診断と臨床管理の指針となる可能性がある。
9)「節外性Rosai-Dorfman病の臨床病理学的特徴: 25 例の後方視的検討」
Clinicopathological characteristics of extranodal Rosai-Dorfman disease: A retrospective case series of 25 patients.
Tran PTC, et al. Ann Diagn Pathol. 2024 Dec;73:152377.
Rosi-Dorfman病(RDD)は、典型的にはリンパ節病変を呈する、まれなnon-LCHである。節外病変はさらにまれで、他の疾患と組織学的特徴が重複し、普遍なバイオマーカーがないため、診断が困難である。サイクリンD1の免疫組織化学(IHC)染色が、節外性RDDの診断に補助的に役立つ可能性がある。2013年1月~2023年12月に節外性RDDと診断された症例を後方視的に解析した。サイクリンD1のIHC染色は、保存された組織検体を用いて行った。RDDの診断を補助するバイオマーカーであるIHC染色の結果、患者の年齢・性別、臨床所見、転帰を抽出した。節外性RDDが25例あり、21例(84%)が女性、4例(16%)が男性であった。診断時年齢は平均42.6歳であった。5例(20%)に皮膚病変、20例(80%)に深部組織病変を認めた。11例(44%)は体幹と四肢に限局した病変を、13例は頭頸部領域(52%)に病変を認め、そのうち5例は鼻および副鼻腔病変であった。追跡データが入手可能であった14例中では、ほとんど(11例; 78.6%)が完全に回復していた。ただし、1例が再発し、1例が失明し、1例が難聴をきたしていた。サイクリンD1の IHC染色は全例が陽性であり、以前の研究と一致していた。この研究の臨床病理学的所見により、病変が分布する部位、病変部位に関連する後遺症の可能性、サイクリンD1のIHC染色の診断的有用性が明らかとなった。
10)「播種性黄色腫の臨床的特徴と治療転帰に関する系統的レビュー」
A Systematic Review of Clinical Features and Treatment Outcomes of Xanthoma Disseminatum.
Mija LA, et al. J Cutan Med Surg. 2024 Nov-Dec;28(6):572-576.
播種性黄色腫 (XD) は、皮膚のnon-LCHに属するまれな血中脂質は正常の皮膚粘膜黄色腫症である。XDの診療には大きな課題があり、情報は少ない。XDの臨床的特徴と治療転帰に関する既存の文献を包括的に評価することを目的とした。「播種性黄色腫」と「モンゴメリー症候群」を検索語とし、MEDLINE、Embase、PubMedを体系的に検索した。2名のレビュー担当者によって二重に検索した。151件の論文が選択基準を満たし、166例のXD(女性106、男性60)が抽出された。診断時の平均年齢は35.3歳(範囲: 9か月~87歳)であった。XDは、通常、黄色から茶色の癒合性丘疹/斑および結節を呈した。皮疹の部位は、主に顔面(116/166例)、屈曲部(45/166例)、体幹(65/166例)、生殖器/鼠径部(63/166例)であった。ほとんどの症例(165/166例:99.4%)に下垂体や中咽頭などの皮膚外病変が見られた。治療は様々で完全奏効率 (CRR) は低くかった。治療転帰が示されている例が99例あり、CCRは外科的切除(4/17例、23.5%)、全身ステロイド(2/40例、5.0%)、免疫抑制剤/免疫調節剤(7/73例、9.6%)、energy-based device(高周波・超音波・強力パルス光・ラジオ波など)(1/7例、14.3%)、高脂血症治療薬(1/24例、4.2%)、凍結療法(1/ 6例、16.7%)、レーザー(1/10例、10.0%)、局所ステロイド(0/ 6例、0%)、経口レチノイド(0/2例、0%)、放射線療法(0/5例、0%)であった。最も有望な治療法はクラドリビンで、報告されたすべての治療法の中で CRR が 27.1%(6/22例)と最も高く、無反応率は9.1%(2/22例)と最も低かった。このレビューでは、XD において全身症状を呈することが多いことが確認された。治療の選択肢は多岐にわたるため、この困難な病状の管理戦略を確立するにはさらなる研究が必要である。