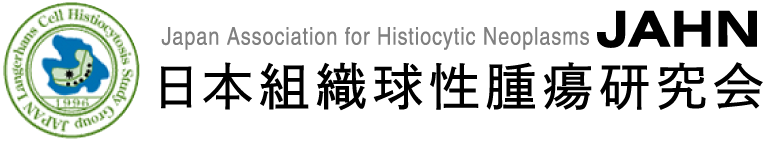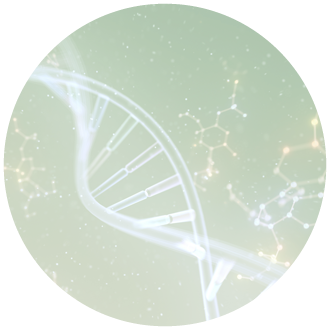最新学術情報
第74回 最新学術情報
1)「肺LCHの予後は努力性1秒呼気量の経時的変化によって2分される」
Two forced expiratory volume in 1 s trajectories with distinct prognoses in pulmonary Langerhans cell histiocytosis.
Benattia A, et al. ERJ Open Res. 2025 Feb 25;11(1):00864-2024.
【背景】肺LCH患者の肺機能の転帰は多様であり予測困難である。本研究は、肺LCH患者の長期追跡調査において、努力性1秒呼気量(FEV1)の経時的変化パターンを特定することを目的とした。【方法】2004年1月~2018年4月に新規診断された肺LCHの成人患者を本研究の前方視的研究の対象とした。主要評価項目は、縦断的データおよびイベント発生時間データに対する結合潜在クラスモデルを用いたFEV1経時的変化パターンの同定であった。内部検証はブートストラップ法により実施した。【結果】191例(平均年齢39±12歳、女性59%、喫煙者96%)を対象とした追跡期間の中央値5.1年(四分位範囲3.2~6.0)の調査により、2つのFEV1の経時的変化パターンが同定された。パターン1(157例、82.2%)は、診断時のFEV1が正常(平均予測値95±3%)で経時的に安定していた(年間変動0.2%、95%信頼区間: -0.8~0.4)。パターン2(34例、17.8%)は、初期にFEV1が低値(予測値の63±7%)で、予測値の年間減少率は-1.8%(-3.4~-0.2)であった。パターン2の群は死亡率が高かった(ハザード比9.46、95%信頼区間1.24~72.2、p=0.03)。【結論】ほとんどの肺LCH患者においてFEV1は安定していたが、経時的にFEV1が有意に低下した患者群は予後不良であった。これらの患者は、早期の治療介入のために綿密なモニタリングが必要である。これらの結果は、外部検証コホートで確認する必要がある。
2)「小児LCHにおける遺伝子変異と予後への影響」
Genetic Landscape and Its Prognostic Impact in Children With Langerhans Cell Histiocytosis.
Wang CJ, et al. Arch Pathol Lab Med. 2025 Feb 1;149(2):175-190.
【背景】LCHは主に幼児に発症するまれな骨髄腫瘍である。【目的】小児LCHにおける遺伝子変異と、臨床的特徴および予後との関連を調査することを目的とした。【方法】小児LCHの病変部位での変異を検出するために、ターゲットシークエンスを行った。【結果】223例のうち187例(83.9%)で、MAPK経路の5つの遺伝子に計30の遺伝子変異が見出された。BRAF600Eが最も多い変異(51.6%)で、次いでMAP2K1変異(17.0%)、その他のBRAF変異(13.0%)が多かった。ARAFおよびKRAS変異は比較的まれであった(それぞれ2.2%と0.9%)。さらに、ERK1/2リン酸化による恒常的活性化の可能性がある、FNBP1::BRAF融合、MAP3K10変異(A17TとR823C)をそれぞれ1例で認めた。BRAF600Eはリスク臓器病変のある例でより多く、一方MAP2K1変異は単一臓器型の例でより多く見られた(P=0.001)。BRAF600Eは頭蓋顔面骨、皮膚、肝臓、脾臓、耳病変と関連していた(全てP<0.05)。その他のBRAF変異を持つ患者は脊柱病変の割合が高かった(P=0.006)。単変量解析では、第一選択療法(ビンブラスチン/プレドノゾロン)を受けた例において4つの分子サブグループ(BRAF600E、MAP2K1変異、その他のBRAF変異、その他の変異)間で無増悪生存率に有意差を認めた(P=0.02)。多変量解析では、リスク臓器浸潤は最も強い独立した予後不良因子であった(ハザード比8.854, P<0.001)。BRAF変異やMAP2K1変異は独立した予後因子ではなかった。【結論】小児のLCH患者のほとんどはMAPK経路の遺伝子に体細胞変異を有しており、臨床的特徴や第一選択化学療法の治療反応と関連している。
3)「成人LCH患者に対するメトトレキサートとシタラビン療法の長期追跡調査」
Long-term follow-up of methotrexate and cytarabine in adult patients with Langerhans cell histiocytosis.
Lin H, et al. Br J Haematol. 2025 Feb;206(2):576-584.
成人LCHの最適な治療戦略は依然として不明である。我々は既に、追跡期間の中央値は2年で、新たに診断された成人LCHに対するメトトレキサート(MTX)とシタラビン(Ara-C)の併用療法の顕著な有効性を示した。本論文では、2014年1月から2020年12月の間に実施した単群単施設前向き第2相臨床試験(NCT02389400)から得られた、長期追跡データ(追跡期間の中央値78か月 (6.5年))を報告する。多臓器病変または多発性単一臓器病変を呈する新たに診断された成人LCH患者95例が、35日毎に6サイクルのMTX/Ara-C療法を受けた。1日目にMTX(1 g/m2)を24時間点滴で、1-5日目に Ara-C(0.1 g/m2)を24時間点滴で投与した。主要評価項目は無イベント生存率(EFS)であった。患者の年齢中央値は32歳(範囲18~65歳)であった。全奏効率は89.5%であった。7例が死亡し、38例が再発した。中枢神経変性症を続発した例はなかった。6年全生存率(OS)およびEFS率の推定値はそれぞれ93.2%、55.2%であった。多変量解析により、診断時でのリスク臓器(RO)浸潤(ハザード比[HR] 6.135 [95%信頼区間(CI)1.185-32.259]、p = 0.031)および診断時年齢が40歳超(HR 7.299 [95% CI 1.056-21.277]、p=0.042)がOS不良因子であった。診断時でのRO浸潤(HR 2.604 [95% CI 1.418-4.762]、p=0.002)および皮膚病変(HR 2.232 [95% CI 1.171-4.255]、p=0.015)はEFS不良因子であった。有害事象として、4例に二次原発性悪性腫瘍が発生した。結論として、MA療法は新たに診断された成人LCH患者にとって有効かつ安全な治療法である。
4)「BRAF600EはiPSCに特有の表現型と薬剤反応示すLCHの重要な特徴を誘導する」
BRAF600E induces key features of LCH in iPSCs with cell type-specific phenotypes and drug responses.
Abagnale G, et al. Blood. 2025 Feb 20;145(8):850-865.
LCHはCD1a陽性/CD207陽性細胞を含む腫瘍性病変によって定義されるクローン性造血障害である。LCHの2つの重篤な合併症は、全身性過剰炎症と進行性神経変性である。腫瘍検体の不足と適切なモデルがないことから、LCHの病因と発症機序の理解は困難であり、患者の診療に影響を及ぼしている。LCHの最も一般的なドライバー変異である BRAF600E変異を持つ人工多能性幹細胞(iPSC)を用いて、LCHのヒトin vitroモデルを作成した。BRAF600E/WT iPSCは造血過程で骨髄単球への分化偏向を示し、CD14陽性前駆細胞に由来する病変部のLCH細胞に類似したCD1a陽性/CD207陽性細胞に自発的に分化した。BRAF600Eは単球分化を制御する主要な転写因子の発現を調節し、骨髄分化の初期段階で炎症誘発性分子とLCHマーカー遺伝子発現の上方制御につながることが明らかとなった。in vitro薬物試験により、BRAF600Eにより誘発されるトランスクリプトームの変化は、MAPK経路阻害剤(MAPKi)による治療で元に戻ることが明らかになった。重要なことは、MAPKiは骨髄前駆細胞に影響せず、成熟したCD14陽性細胞集団のみを減少させたことである。さらに、iPSC由来CD34陽性前駆細胞から分化したBRAF600E/WT iPSC由来ミクログリア様細胞(iMGL)と共培養したiPSC由来神経細胞(iNeurons)は、神経細胞の損傷とニューロフィラメント軽鎖の放出を伴う神経変性の兆候を示した。要約すると、ここで説明したiPSCベースのモデルは、さまざまな造血細胞タイプにおけるBRAF600Eの影響を解析するためのモデルとなり、BRAF600Eにより発症する疾患に対する治療法を見出したり新しい治療法を比較したりするための手段となる。
5)「IRF8は組織球性腫瘍および樹状細胞腫瘍の多くの例で陽性である」
IRF8 Demonstrates Positivity in a Significant Subset of Histiocytic and Dendritic Cell Neoplasms.
Patwardhan PP, et al. Am J Surg Pathol. 2025 Feb 1;49(2):98-103.
組織球性および樹状細胞性腫瘍、特に組織球性肉腫は、未熟な単球性腫瘍と形態学的および免疫組織学的に鑑別が難しい。IRF8の免疫組織化学染色は単芽球の同定に有効であることが実証されているが、組織球性および樹状細胞性腫瘍ではあまり研究されていない。組織球性肉腫(HS、6例)、LCH(25例)、Rosai-Dorfman病(RDD、17例)、濾胞性樹状細胞肉腫(FDCS、3例)、Erdheim-Chester病(ECD、5例)と、単球分化を伴う骨髄性腫瘍を含む例を対照群として、IRF8の免疫組織化学染色を行った。計89例のうち、HSの6例中3例、ECDの5例中3例、RDDの17例中12例、LCHの25例中7例、FDCSでは3例中0例でIRF8が陽性であった。対照群では以前の報告と同様の染色性を示し、IRF8発現は単芽球数とほぼ相関し、他の対照群においては正常に染色された。IRF8は、組織球系および樹状細胞系の腫瘍の多くで発現している。IRF8が単芽球の識別に有用であることが確認されたが、これらの結果は、IRF8が組織球性肉腫と単球系骨髄性腫瘍を区別するのには役立たないことを示しており、そのような場合のIRF8染色の解釈には注意が必要である。
6)「小児LCHの臨床的特徴と予後因子:単施設の後方視的研究」
Clinical features and prognostic factors of pediatric Langerhans cell histiocytosis: a single-center retrospective study.
Lu Y, et al. Front Med (Lausanne). 2025 Jan 15;11:1452003.
【目的】中国の単施設で治療を受けた小児LCH患者の臨床的特徴と予後因子を後方視的に評価する。【方法】中国済南市の山東第一医学大学付属省立病院において、SD-LCHプロトコルに従って小児LCHを治療した。最近経験した82例のLCHを対象に、初期症状、治療法、長期転帰を後方視的に評価した。追跡調査は2023年7月31日まで実施した。【結果】診断時年齢は中央値2歳(0.25~12歳)であった。 SS-LCHが42例(51.2%)、MS-LCHが40例(48.8%)であった。最も多い病変臓器は骨(82.9%)であった。16年間の追跡期間で5年EFS率およびOS率はそれぞれ75.2 ± 5%、90.9 ± 3.3%であった。累積再発率は23.2%であった。SS-LCH群とMS-LCH群の5年EFS率はそれぞれ90.2±4.6%と58.8±8.3%、5年OS率はそれぞれ90.2±4.6%と81.2±6.5%であった。 RO+ LCH患者とRO- LCH患者の5年OSおよびEFS率は、それぞれ79.5±7.5%、53.8±9.6%、87.5±11.7%、76.2±14.8%であり、有意差はなかった。多変量Cox回帰分析の結果、肝病変はEFS不良因子、血液病変は独立したOS不良因子であった。2017年以降、BRAF600E遺伝子変異の検出と分子標的治療は予後を有意に改善した。【結論】肝病変と血液病変は予後不良を示唆し、SD-LCHプロトコルは小児LCH患者の予後を改善する。
7)「小児LCH:診断および経過観察における超音波検査の意義」
Langerhans cell histiocytosis in children: the value of ultrasound in diagnosis and follow-up.
Yang J, et al. BMC Med Imaging. 2025 Jan 29;25(1):29.
【背景】LCHは稀な疾患であり、小児に最も多くみられる。超音波検査は非侵襲的で安価であり、広く普及している検査法である。しかし、LCHの超音波画像所見および治療反応評価や経過観察における意義に関する体系的な研究は比較的少なく、LCHの診断および経過観察における超音波検査の臨床的意義は全体的に過小評価されている。【目的】本研究は、LCHの超音波画像所見を他の画像検査と比較し、小児LCHの経過観察における超音波検査の意義を評価することを目的とした。【症例と方法】小児LCH 44例(女児19例、男児25例、年齢:中央値60か月、範囲8~192か月)を後方視的に分析した。44例中31例が単一臓器型(SS-LCH)、13例が多臓器型(MS-LCH)であった。臨床的特徴、超音波画像、X線・CT・MRIなどの他の手段による画像を解析した。特に骨、甲状腺、肝臓といった様々な病変の超音波画像の特徴を分析し、様々な画像手段によって正しく同定された症例の割合を評価した。【結果】局所的な虫食い状の骨欠損病変を38例で計43個の認め、超音波では境界明瞭な低エコー病変を示した。5例は肝臓に低エコーまたは高エコー領域を呈した。 2例は甲状腺に散在性またはびまん性の不規則な低エコー領域を呈した。骨病変のある2例と甲状腺病変のある1例は化学療法後に病変の縮小と血流低下が認め、6個の肝臓病変は超音波検査で消失または縮小した。骨病変における超音波の正診率(65.38%)は、X線(21.05%)の正診率(P=0.026)よりも高く、CTおよびMRIの正診率と同程度であった。LCHに対する超音波の全体的な正診率は、他の画像診断法と有意差はなかった。【結論】LCH病変は超音波によって検出および疑診することができる。超音波は小児LCHの診断および経過観察に優れたツールとなる可能性がある。
8)「骨髄細胞およびリンパ球系細胞におけるドライバー変異は、多様な組織球性腫瘍の多能性前駆細胞起源を示唆する」
Driver mutations in myeloid and lymphoid cells point to multipotent progenitor origin of diverse histiocytic neoplasms.
van Halteren AGS, et al. Blood Neoplasia. 2025 Jan 27;2(2):100074.
組織球性腫瘍は、MAPK経路を活性化する遺伝子変異を特徴とする稀な骨髄疾患である。Non-LCH組織球症に焦点を当て、その造血起源を解析した。組織球症病変で検出されたBRAF、MAP2K1、KRAS遺伝子の変異を特異的に検出するddPCRアッセイを用いることで、14例中13例において、末梢血の血球中に同一のドライバー変異を検出した。13例中9例において、末梢血中のリンパ球系細胞に変異が検出され、多能性前駆細胞がこれらの変異を獲得した可能性が高いことが示唆された。9例中5例は単一臓器型の成人で、そのうち3例は再発性皮膚黄色肉芽腫であった。これら3例において、最長25年後の再発した黄色肉芽腫で同一のKRASまたはBRAF変異が検出されたことから、長寿命の変異陽性の前駆細胞の存在が裏付けられた。概念実証として、3例中1例でドライバー変異が末梢血中のCD34陽性前駆細胞に確認された。この症例の別の黄色肉芽腫病変でKRAS、BRAF、ARAFのいずれかの二次変異が特定され、これらの再発病変の形成の根底にある2ヒット変異プロセスが示唆された。最後に、末梢血中に変異陽性細胞が存在しなかった唯一の孤発性LCHの患者の病変で、同一のKRAS変異を有する組織球とB細胞が検出された。これらのデータは、多能性造血前駆細胞が単一臓器および多臓器型組織球症の両者の起源細胞であることを示している。
9)「肺LCHの成人コホートにおける高解像度胸部CTによる反応評価」
High resolution chest computed tomography responses for a cohort of adult with pulmonary Langerhans cell histiocytosis.
Chang L, et al. Ann Hematol. 2025 Jan;104(1):65-74.
LCHは、さまざまな肺の症状と画像所見を示す不均一な組織球症である。継続的な追跡調査を通じて高解像度胸部CT(HRCT)によって肺LCHの治療反応性を評価することを目的とした。肺病変のある73例の成人LCH患者を後方視的に分析した。診断時と治療後のHRCTグローバルスコア(結節スコアと嚢胞スコア)の変化を評価した。69例(94.5%)は肺病変を伴う多臓器型LCHであった。42例がメトトレキサートとシタラビンの併用療法、15例がシタラビン単独療法、7例が分子標的療法を受けた。14例(19.2%)が完全奏効(CR)、45例(61.6%)が部分奏効(PR)を得た。全肺病変スコアの平均値は12.2 から 10.6 に低下した。結節スコアの平均値は 4.7 から 4.1 に、嚢胞スコアの平均値は 7.4 から 6.5 に低下した。HRCTグローバルスコアの評価では、25例(34.2%)はスコアが低下し反応あり、3例(4.1%)はスコアが上昇し病変進行、45例(61.6%)はスコアが変わらず不変と判定された。 CRまたはPRの例のうち、それぞれ57.1%と40.5%が HRCTグローバルスコアが低下したのに対し、SDまたはPDの例ではHRCTスコアが低下した例はなかった。多変量解析により、低用量シタラビン療法を受けた患者とHRCTグローバルスコア≥10の例は無増悪生存期間が短いことが明らかになった。
10)「組織球性肉腫における転写発現比較を用いた免疫抑制候補の特定」
Identification of immune suppressor candidates utilizing comparative transcriptional profiling in histiocytic sarcoma.
Lenz JA, et al. Cancer Immunol Immunother. 2025 Jan 3;74(2):61.
組織球性肉腫(HS)は、確立された標準治療のない、まれではあるが致命的な悪性腫瘍である。前臨床モデルがないため、HSの病因の理解と治療標的の特定が困難である。犬のHSは、ヒトのHSと臨床的および遺伝学的に多くの類似点を共有しており、ユニークなトランスレーショナルモデルとしての使用できる可能性がある。これまでは、HSの免疫原性について研究されてきた。腫瘍浸潤リンパ球(TIL)が多いHSの犬の予後は良い傾向にあるが、事実上すべてのHSの犬は、最終的には抗腫瘍免疫の破綻とともに疾患が進行してしまう。免疫腫瘍微小環境の潜在的な調節因子を探索するため、高度のT細胞浸潤を伴い長期生存している肺HSの犬3例、顕著なT細胞浸潤を伴わない生存期間が短い脾臓HSに犬3例において、がんに罹患していない犬の肉眼的に正常な組織と転写発現を比較した。この比較により、免疫チェックポイントPD-1をコードするPDCD1と、分泌型腫瘍形成促進タンパク質オステオポンチンをコードするSPP1が、犬のHSにおいて高発現しており発現差がある遺伝子 (DEG) として特定された。腫瘍抑制因子TXNIPをコードするTXNIPは、最も重要な低発現のDEGであった。比較トランスクリプトーム研究により、犬のHSとヒトの HS を比較したところ、高発現のDEG(SPP1を含む)と低発現のDEG(TXNIPを含む)が共通していることが明らかになった。免疫組織化学により、犬とヒトのHSの免疫腫瘍微小環境にオステオポンチンが存在することが実証された。総合的に、我々はPD-1、オステオポンチン、TXNIPがHSにおける実行可能な標的であることを明らかにし、犬のHSはこの致命的な疾患に対する新しい免疫療法アプローチをスクリーニングするための前臨床モデルとなることを確立した。