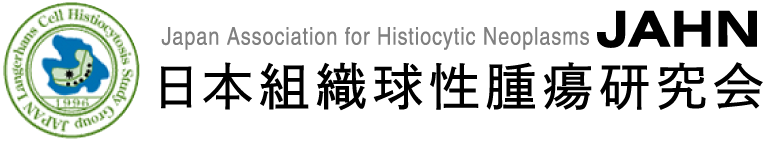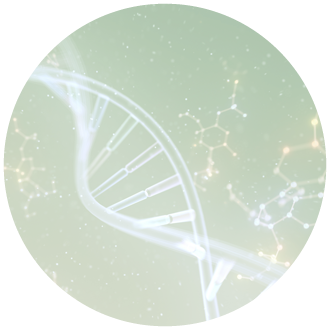最新学術情報
第76回 最新学術情報
1)「成人LCH患者においてデノスマブ治療中止後の骨代謝のリバウンドは認めない:前向き臨床試験」
No overshoot of bone turnover after withdrawal of denosumab treatment of adults with Langerhans cell histiocytosis: a prospective clinical trial.
Makras P, et al. Osteoporos Int. 2025 Jul;36(7):1231-1237.
骨粗鬆症において、デノスマブ(Dmab)の投与中止は骨代謝のリバウンドにつながるが、その原因は依然としてほぼ不明である。前向き試験において、Dmab治療を受けたLCH例は、短期間の高用量投与にもかかわらず、骨代謝マーカーのリバウンドを示さなかった。この結果は、Dmabの総投与量が骨代謝マーカーのリバウンドを引き起こすわけではないことを示している。【目的】Dmab治療を受けた骨粗鬆症患者において、その投与期間は投与中止後の骨代謝マーカーのリバウンドの重要なリスク因子となる。このことが、Dmabの総投与量に関連するのか、骨粗鬆症の重症度に関連するのかは不明である。この問題を解明するには、骨粗鬆症で使用される用量よりも高用量のDmabを投与し、中止後の骨代謝の変化を長期にわたって追跡することが不可欠である。【方法】前向き単群非盲検第IIb相臨床試験において、成人LCH 10例(骨病変を有する8例 [単発4例、多発4例]、骨病変を有しない2例)を対象に、Dmab 120 mg/2か月を4回(総量480 mg)皮下注射し、最終投与後24か月間追跡調査した。【結果】治療により骨代謝マーカーは治療前値の約10%に低下したが、治療中止後には治療前値を超えない値まで上昇し、血清CTXピーク値は平均(±SD)は0.522 ± 0.366 ng/mL、P1NPピーク値は72.2 ± 35.9 ng/mLであり、治療前値と有意差を認めなかった(それぞれp=0.11, 0.65)。さらに、治療前値と血清CTXピーク値は有意に相関していた(rs=0.818, p=0.007)。椎体骨折、骨量減少、高カルシウム血症は認めなかった。【結論】LCHに対して、骨粗鬆症に対して4年間で投与されるのと同量のDmabを6か月間で投与したにもかかわらず、Dmab投与中止後の骨代謝マーカーのオーバーシュートや骨量減少は認めなかった。したがって、Dmab総投与量は治療中止後の骨代謝オーバーシュートの重要な決定因子ではない。
2)「日本における小児Rosai-Dorfman-Destombes病の全国調査:キナーゼ経路の遺伝子変異を高頻度に認める」
Retrospective nationwide survey of pediatric RDD in Japan: a high prevalence of mutations in the kinase pathway genes.
Asano T, et al. Int J Hematol. 2025 Jul;122(1):128-137.
【背景】Rosai-Dorfman-Destombes病(RDD)は、S100蛋白陽性/CD1a陰性組織球の集積と細胞内細胞嵌入現象を特徴とするまれな組織球症である。近年、RDD患者の約半数で、MAPK経路の遺伝子に発がん性変異が報告されている。【方法】日本において小児RDDの後方視的全国調査を実施した。【結果】9例(男5例、女4例)が見出され、診断時年齢は中央値8歳3か月(範囲:9か月~15歳5か月)であった。2例はリンパ節病変のみ、3例はリンパ節外病変のみ、4例はリンパ節とリンパ節外の両方に病変を認めた。全例でPD-L1の発現を認めた。2例は無治療で寛解した。3例はプレドニゾロン、1例は手術と放射線療法、3例は化学療法を受けた。2例は糸球体腎炎を合併していた。遺伝子変異解析をした6例中5例でキナーゼ経路の遺伝子に発がん性体細胞変異を認めた(MAP2K1 3例、KRAS 1例、TSC1 1例)。MAP2K1変異を有する化学療法抵抗性の2例はトラメチニブが有効であった。追跡期間の中央値4年9か月で、2例が原病死亡した。【結論】小児RDD例のほとんどはキナーゼ経路に遺伝子変異を有する。難治例には変異解析が推奨される。
3)「神経変性LCHにおける定量的脳MRI解析」
Quantitative Brain MRI Analysis in Neurodegenerative Langerhans Cell Histiocytosis.
Baek C, et al. Eur J Neurol. 2025 Jun;32(6):e70249.
【背景】神経変性LCH(ND-LCH)は、LCHに続発する重篤な中枢神経系障害である。ND-LCHは、小脳失調、錐体路徴候、仮性球麻痺、認知障害、行動障害を特徴とする。小脳萎縮は最もよくみられるMRI所見で、文献で広く報告されている。しかし、小脳の容積変化の自然経過についてはこれまで検討されていない。本研究では、ND-LCH例と対照群における小脳萎縮の定量解析を行った。【方法】ND-LCH例のMRIを対照群と比較した。Volbrainソフトウェア(CERES)を用いて自動小脳解析を実施し、線型回帰分析を用いて経時的な小脳萎縮の重症度を評価した。【結果】成人ND-LCH 16例と対照群22名のMRI所見を比較した。追跡期間は中央値6年間で、1例あたり平均4枚のMRIを解析した。ND-LCH例は全例で経時的に小脳全体および皮質の萎縮を示した。平均萎縮率は-1.86 cm³/年(範囲-5.90~0.34)で、患者間でばらつきがあった。全ての小脳小葉に萎縮をみとめた。【結論】ND-LCHにおける小脳の縦断的定量的MRI解析は、(i)実施可能であり、(ii)ND-LCH例において経時的に小脳全体および皮質の有意な萎縮を確認し、(iii)小脳萎縮の進行速度を推定し、(iv)臨床的に進行が緩やかな疾患における治療効果の指標として有用性がある。。本研究の結果を検証するには、さらなる研究が必要である。
4)「組織球症患者における中心窩下脈絡膜の厚さと脈絡膜浸潤のマルチモーダル画像特徴」
Subfoveal Choroidal Thickness in Patients with Histiocytosis and Multimodal Imaging Features of Choroidal Infiltrates.
Francis JH, et al. Ophthalmol Retina. 2025 Jun;9(6):580-588.
【目的】組織球症患者の中心窩下脈絡膜の厚さ(SFCT)を含む脈絡膜所見、眼底検査で可視化される脈絡膜浸潤病変に対するマルチモーダル画像を評価し、これらの異常が組織球症に対する標的治療(キナーゼ阻害剤)で変化するかどうかを判定する。【対象】組織球症患者91例と年齢・性別を一致させた対照群41例。【デザイン】単一の三次がん紹介センターでの後方視的比較研究。【方法】臨床検査、眼底写真、OCTを用いて、脈絡膜所見を評価した。眼底検査で臨床的に明らかな脈絡膜浸潤を記録し、脈絡膜血管構造を定性的に検査した。SFCT は、ブルッフ膜の外側部分から脈絡膜強膜界面までを、深度イメージング強化スペクトル領域光干渉断層法 (EDI SD-OCT) を用いて測定した。【主要評価項目】対照群と比較したSFCT。副次評価項目は、組織球症に対する標的療法(キナーゼ阻害剤)による SFCT の変化、眼底検査で可視化される脈絡膜浸潤のマルチモーダル画像。【結果】組織球症91例(Erdheim-Chester病 35例、Rosai-Dorfman病 21例、黄色肉芽腫 7例、混合組織球症 11例、LCH 15例、その他 2例;男性 46例、女性 45例) の182眼を解析した。組織球症患者のSFCT(336.2±94.9 μm)は、対照群(250.3±60.7 μm)と比べ有意に厚かった(p<0.0001)。SFCTが275 μmを超える症例の割合は、組織球症患者で69%、対照群で27%と有意差があった(p<0.0001)。SFCTは、組織球症のサブタイプ、骨病変や中枢神経病変の有無、眼後極部、その他の眼病変の有無、遺伝子変異プロファイルとは相関していなかった。6か月を超える追跡調査を受けた、治療歴のない35例のサブグループ分析では、組織球症を標的とした治療(キナーゼ阻害剤)により、SFCTが275 μmを超える症例の割合は有意に減少した(p=0.0016)。臨床的に明らかな脈絡膜浸潤が19.8%に認められた。大多数は黄白色で地図状、後極部に位置し、高自家蛍光を示した。OCTでは、浸潤病変に隣接するHaller静脈の拡大、脈絡膜毛細管の圧排、脈絡膜構造の消失を認めた。【結論】このコホートでは、組織球症患者の19.8%に臨床的に明らかな脈絡膜浸潤が見られた。さらに、組織球症患者の大多数は、年齢・性別を一致させた対照群と比較して、中心窩下脈絡膜が有意に肥厚していた。組織球症を標的とした治療(キナーゼ阻害剤)により、脈絡膜の肥厚は減少し、全身治療の反応性の指標となる可能性がある。
5)「BRAF阻害薬単剤治療によるErdheim-Chester病の長期転帰」
Long-term outcomes with single-agent BRAF inhibitor therapy in Erdheim-Chester disease.
Goyal G, et al. Blood. 2025 May 1;145(18):2100-2103.
BRAF阻害薬単剤で治療された64例のErdheim-Chester病の患者を解析したところ(追跡期間の中央値4年)、奏効率は85%と高かったが、61%が、有害事象が主な原因で、治療中断を余儀なくされた。さらに、患者は健康関連の生活の質は低く、症状の負担は大きかった。
6)「LCHの評価における[68Ga]Ga-FAPI PET/CTの有用性: [18F]FDG PET/CTとの比較」
[(68)Ga]Ga-FAPI PET/CT in the evaluation of Langerhans cell histiocytosis: comparison with [(18)F]FDG PET/CT.
Zhang W, et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2025 May;52(6):2187-2197.
【目的】LCHの評価において、[68Ga]Ga-FAPI PET/CTが、[18F]FDG PET/CTと比較し有用であるか検討することを目的とした。【方法】病理学的にLCHと診断された32例を対象とした。病変の範囲と状態を明らかにするため、[68Ga]Ga-FAPIと[18F]FDG PET/CTを1週間以内の間隔で実施した。病変部位の検出率と集積強度を比較した。【結果】活動性疾患が30例、非活動性疾患が2例であった。活動性疾患の例において、最も多く検出された病変部位は骨(30例中27例)で、[68Ga]Ga-FAPI PET/CTでは[18F]FDG PET/CTよりも多くの骨病変の検出が可能であった(106/106病変 vs. 52/106病変)。 [68Ga]Ga-FAPIでは、[18F]FDGでは見逃されることが多かった肝臓、皮膚、唾液腺の病変も同定できた。両者とも胸腺や下垂体の病変を検出できたが、[68Ga]Ga-FAPIの方がよりコントラストが高く診断信頼性が高かった。しかし、リンパ節病変は[68Ga]Ga-FAPIでは描出されなかった。[68Ga]Ga-FAPIの優れた感度によって、約30%(30例中10例)で病型が再判定された。さらに、[68Ga]Ga-FAPIは治療効果判定においても優れていると考えられた。【結論】[68Ga]Ga-FAPI PET/CTは、LCHにおける骨病変およびリンパ節以外の病変の検出において[18F]FDG PET/CTを上回り、正確な病変評価と治療戦略の立案に有用なツールとなる。
7)「フランスにおける141例の悪性組織球症の後方視的ケースシリーズにおける疾患の特徴と治療結果」
Characterization and Treatment Outcomes of Malignant Histiocytoses in a Retrospective Series of 141 Cases in France.
Bigenwald C Dr, et al. 2025 May 27;9(10):2530-2541..
悪性組織球症(MH)はまれで、十分に理解されていない悪性腫瘍であり、確立された治療ガイドラインはない。本研究では、2000年~2023年にフランスで診断されたMHについて全国的後方視的研究を実施した。全例に中央病理組織学的再評価を行い、組織球が間質に非常に多い悪性腫瘍は除外した。計141例が対象となり、年齢は中央値 62歳(範囲:1歳~87歳)であった。症例の64%が原発性MH、36%が他の造血悪性腫瘍に関連した二次性MHであった。WHO分類に基づく病型は、組織球性肉腫(43%)、嵌合性樹状細胞肉腫(37%)、ランゲルハンス細胞肉腫(12%)、高悪性度不確定樹状細胞腫瘍(10%)であった。腫瘍細胞はほぼ全例でCSF1RとPU.1陽性で、85%がリン酸化 ERK陽性であった。次世代シーケンスが75例で実施された。MAPK経路の変異は、原発性MHと比較し、二次性MHでより高頻度に認めた(90% vs. 55%, p=0.0012)。PTPN11変異は原発性MHにのみ認めた(p=0.0035)。DNAメチル化関連遺伝子(TET2、ASXL1、DNMT3A)の変異を20%、TP53変異を14%に認めた。治療レジメンは様々であったが、局所病変に対する外科的切除例、BRAFまたはMEK 阻害剤使用例の完全奏功率は、それぞれ63%、21%と最も高かった。しかし、全体としての予後は依然として不良で5年全生存率は31%と、T/NK細胞リンパ腫と同等であった。患者の生存率を改善するには、前向きな追跡調査と専門施設での標準化された治療戦略の確立が不可欠である。
8)「LCHの遺伝子差異解析とMMP1標的薬物再配置の重要性」
Differential Gene Analysis of Langerhans Cell Histiocytosis and the Significance of MMP1-Targeted Drug Repositioning.
Feng X, et al. Mol Biotechnol. 2025 May;67(5):2098-2110.
LCHは、主に幼児に発症するまれな疾患である。MAPK経路の活性化により、LCHの病因に関する重要な新たな知見が得られたが、その発生と発症の正確なメカニズムは、まだ完全に解明されていない。多臓器型LCHは、再発率が依然として高い。そのため、本研究では、他のLCHの潜在的な病態と将来の治療標的について研究することを目的とした。遺伝子発現包括(GEO)データベースを用い、LCH(GSE16395)の遺伝子発現プロファイルを取得した。LCHにおいて共通して発現が異なる遺伝子(DEG)を特定し、ハブ遺伝子の特定、機能的意味付け、モジュール構築、薬剤の再配置、免疫組織化学(IHC)による発現分析という3つの異なるタイプの分析を行った。417個のDEGと50個の中心的なハブ遺伝子を特定した。これら遺伝子の機能として、角質化、皮膚の発生、炎症の重要性が挙げられた。さらに、LCH治療に使用できる新しい薬剤として、マトリックスメタロプロテアーゼ1:MMP1を標的とするRS2薬剤が候補として挙がった。最後に、遺伝子-miRNAと遺伝子-TFネットワーク、および免疫細胞浸潤を分析し、MMP1関連遺伝子を解析した。LCH組織におけるMMP1発現レベルはIHCによって検証された。この研究により、中心となる共通遺伝子と新しい薬剤候補が特定された。これらの共有経路とハブ遺伝子は、候補薬剤の作用機序と治療標的について新しい展望を提供する。
9)「顎骨LCH:68症例の臨床解析」
Langerhans cell histiocytosis of the jaw: clinical analysis of 68 cases.
Li J, et al. Orphanet J Rare Dis. 2025 Apr 21;20(1):191..
【背景】本研究は、顎骨LCHの臨床的特徴、画像所見、治療、予後因子を分析し、臨床診断および管理に有益な知見を提示することを目的とした。【方法】2010年1月~2024年1月に治療を受けた顎骨LCH患者の臨床および追跡データを後方視的に解析した。性別、年齢、症状、画像所見、治療戦略、転帰の情報を収集した。治療転帰に影響する因子を同定するため、SASソフトウェアを用いて単変量および多変量Cox回帰解析を行い、P≦0.05を統計学的に有意とした。【結果】計68例(男性50例、女性18例、年齢中央値13.5歳)を対象とした。患者の40%は10歳未満で、71%に下顎骨病変を認めた。病型分類は、単一臓器単発型(SS-s)が49例、単一臓器多発型(SS-m)疾患が10例、多臓器型(MS)が9例であった。主な症状は、顎または歯の痛み(28例)、顔面腫脹(22例)、歯肉潰瘍(10例)、歯の動揺(9例)であった。画像所見では、歯周病様病変(7例)、嚢胞様病変(17例)、骨髄炎様病変(44例)であった。単変量および多変量Cox回帰分析の結果、女性患者は進行リスクが有意に低かった(P=0.014、HR 0.071)のに対し、SS-m患者(P=0.019、HR 4.992)およびMS患者(P=0.030、HR 4.182)は、SS-s患者と比較して進行リスクが高かった。嚢胞様病変(P=0.001、HR 0.054)および骨髄炎様病変(P<0.001、HR 0.023)は、歯周病様病変と比較して病変進行リスクが低いことが示唆された。【結論】顎骨LCHは全年齢層で発症する可能性があるが、小児に多くみられる。性別、多発性病変、病変のタイプ(歯周病様)などの因子は、病変進行の予測因子として重要である。SS型顎骨LCHでは、完全外科切除と放射線療法の併用が最も高い治癒率を示した。
10)「CCR6高発現は小児LCHのリスクを高める」
High CCR6 expression increases the risk of pediatric Langerhans cell histiocytosis.
Yao X, et al. Blood Sci. 2025 Apr 16;7(2):e00224.
LCHは、主に小児に発症する稀な疾患である。本疾患の複雑な臨床症状を考慮すると、LCH感受性に関連する特異的バイオマーカーの同定は、迅速な診断とリスク層別化に不可欠である。本研究では、RNAスコープ、免疫組織化学、シークエンシング技術を用いて、小児LCH患者の皮膚標本を解析した。病理組織におけるCCR6発現の上昇とLCHリスク分類との間に顕著な相関が認められた。したがって、CCR6発現はLCHにおける独立したリスク予測因子となる可能性がある。さらに、BRAF V600E遺伝子変異の頻度もリスク層別化と相関していた。 BRAF V600E変異陽性の検体において、MAP2K1に新たな変異(H119YおよびR108Q)を見出した。さらに、CCR6陽性腫瘍病変は、CCR7を高発現するリンパ球の集積を促進する可能性がある。