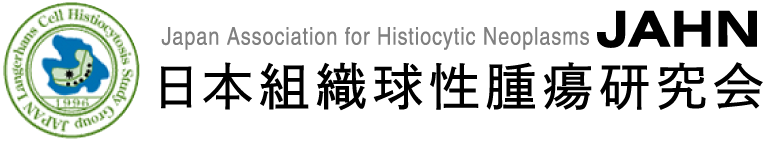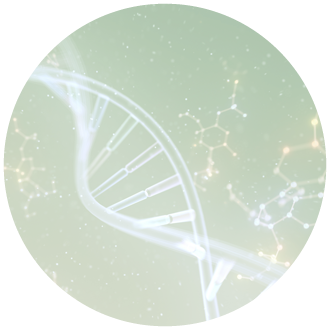最新学術情報
第77回 最新学術情報
1)「小児の側頭骨LCH:システマティックレビュー」
Temporal bone histiocytosis in children: a systematic review.
Galluzzi F, et al. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2025 Aug;195:112436.
【目的】小児の側頭骨LCHの診断、治療、転帰を分析する。【方法】PRISMAガイドラインに基づきシステマティックレビューを実施した。PubMedおよびEmbaseデータベースの文献レビューを実施した。バイアスリスクはMINORスコアを用いて評価した。【結果】84例の小児を対象とした8件の後方視的研究が見つかった。平均年齢は3歳で、男性が多かった。臨床的特徴は、耳漏、耳痛、繰り返す外耳炎・中耳炎、耳介後部の腫脹、皮膚炎、外耳道ポリープ・腫瘤であった。84例中52例(62%)は単一臓器型で、側頭骨以外の臓器浸潤のほとんどは尿崩症を伴う下垂体浸潤であった。CTスキャンでは周囲の硬化を伴わない骨溶解性病変と扁平部の骨打ち抜き病変の所見であった。最も頻度の高い病変部位は乳様突起、外耳、中耳、側頭鱗であり、眼窩と錐体尖は頻度が低かった。3分の1の症例は両側に病変があった。MRIは頭蓋内病変の検出に役立った。伝音性(20例)、感音性(4例)、混合性(5例)の難聴がみられた。治療戦略として、化学療法と放射線療法、化学療法のみ、手術と放射線療法、手術と化学療法があった。全再発率は 20.2 %(84例中17例)であった。追跡期間は6週間から18年であった。側頭骨病変の合併症として、顔面神経麻痺、真珠腫、慢性皮膚炎があった。【結論】小児の側頭骨LCHの診療には、多科のアプローチが必要である。耳鼻咽喉科医の役割は、特定の症例において早期診断と外科的治療に極めて重要である。再発や耳鼻科的合併症を見出すために、長期にわたる経過観察が必要である。
2)「小児期LCH後の慢性的な健康状態: スイス小児がん生存者研究の結果」
Chronic health conditions after childhood Langerhans cell histiocytosis: Results from the Swiss Childhood Cancer Survivor Study.
Sláma T, et al. J Cancer Surviv. 2025 Aug;19(4):1212-1221.
【目的】LCHは、骨髄前駆細胞の異常増殖とそれに続く臓器浸潤を特徴とするまれな疾患である。LCHの予後は良好であるが、生存者の一部は原疾患による慢性的健康問題を抱えることがある。この研究では、LCH生存者と兄弟姉妹を比較し、どのような慢性的健康問題がどのくらいあるのかを評価し、慢性的健康問題に関連する要因を特定することを目的とした。【方法】スイス小児がん生存者研究では、スイス小児がん登録に登録され、1976年~2015年までに診断された5年以上生存しているLCH患者全員に質問票を送付した。兄弟姉妹にも同様の質問票を送付した。LCH生存者と兄弟姉妹の慢性的健康問題の保有率を比較し、ロジスティック回帰を使用して慢性的健康問題の要因を特定した。【結果】計123例のLCH生存者がこの研究に参加し、回答率は69%であった。診断からの経過期間の中央値は13年(四分位範囲9~20)であった。LCH生存者のうち、59%が少なくとも1つの慢性的健康問題を持っていた。兄弟姉妹と比較してLCH生存者では、心血管系(13% vs. 6%)、内分泌系(15% vs. 2%)、筋骨格系(22% vs. 13%)、消化器系(15% vs. 8%)の慢性的健康問題がおおかった(全てp<0.05)。慢性的健康問題の発生と最も強く関連する要因は、多臓器病変、多発性骨病変、下垂体病変であった。【結論】LCHの長期生存者の半数以上が1つ以上の慢性的健康問題を抱えており、兄弟姉妹よりもかなり多かった。【がん生存者への影響】経過観察中のLCH生存者は、特に心血管系、内分泌系、筋骨格系、消化器系の疾患についてスクリーニングを受ける必要がある。
3)「アナキンラはErdheim-Chester病における標的治療の継続率を改善する」
Anakinra improves retention rate of targeted treatments in Erdheim-Chester disease.
Campochiaro C, et al. Rheumatology (Oxford). 2025 Aug 1;64(8):4722-4725.
【目的】Erdheim-Chester病(ECD)は、多様な臨床症状を呈する稀なnon-LCH組織球症である。近年、ECD患者におけるMAPK-ERK経路の活性化変異が同定され、標的治療の導入が進んだ。最も一般的に用いられる標的治療はBRAF阻害薬とMEK阻害薬であり、これらは非常に有効であるが、重大な毒性も伴う。イタリアの2つの紹介センターに入院したECD患者において標的治療の継続率を評価し、アナキンラの併用が治療継続率に影響するかを検証することを目的とした。【方法】分子標的治療薬単独またはアナキンラとの併用療法を受けたECD患者コホートにおける標的治療の継続率を後方視的に解析した。【結果】60コースの標的治療を受けた52例の中で、最も多く使用されたのはベムラフェニブ(72%)で、次いでコビメチニブ(23%)、トラメチニブ(3%)、ダブラフェニブ(2%)であった。全治療コースの18か月での標的治療の継続率は72%で、薬剤間に有意差は認めなかった。治療中止の主な原因は副作用(76%)であった。16例(27%)がアナキンラとの併用療法を受けていた。この併用療法群では、18か月標的治療継続率が有意に高かった(94% vs. 65%, p=0.0251)。生存解析でも、アナキンラ併用群の方が、標的治療の継続率が高かっか(log-rank検定、p = 0.040)。【結論】標的療法を受けたECD患者の18か月間の全奏効率は72%であり、標的治療薬剤による有意差は認められなかった。アナキンラと標的療法の併用により、標的治療の継続率は有意に上昇した。
4)「クラスター分析によりErdheim-Chester病の臨床スペクトルが明らかになった」
Cluster analysis reveals the clinical spectrum of Erdheim-Chester disease.
Tesi M, et al. Leukemia. 2025 Aug;39(8):1987-1996.
Erdheim-Chester病(ECD)は、BRAFなどのMAPK経路のがん遺伝子の変異によって引き起こされるクローン性炎症性腫瘍である。臨床症状は多様で、あらゆる臓器に浸潤することが知られている。本コホート研究では、661例のECDを対象とし、教師なしクラスタリングを用いて臨床的特徴と変異プロファイルに基づき分類した。19の臨床変数と変異変数について、k平均法を用いた階層的クラスタリングを行った。その結果、3クラスターモデルが最も安定したモデルとして検出された。ほとんどの患者は、BRAFV600E変異、大血管・心臓・腎周囲への浸潤といった主要な特徴に基づいて分類された。「広範囲病変」(WID)クラスター(320例、49%)は主要な特徴の存在と関連し、「限定病変」(LIM)クラスター(282例、42%)は主要な特徴の欠如と関連していた。「MAP2K1-RDD」クラスター(MAP)には、MAP2K1変異やRosai-Dorfman-Destombes病(RDD)の重複に基づき、59例(9%)が分類された。生存率解析の結果、LIMと比較し、WIDは予後不良であることが明らかになった(ハザード比1.54、95%信頼区間1.09~2.17)が、MAPでは有意な生存率の低下は認めなかった。変異プロファイル、臓器浸潤、重複病態に基づくこれらのクラスターが特定されたことは、これまでに確立された臨床観察結果を裏付けている。これらの知見は、体細胞変異が何であるかが、ECDの表現型に重要な役割を果たすことを強く示している。
5)「頭蓋顔面LCHに対するトリアムシノロンアセトニド病変内注射の治療奏功:後方視的研究」
Craniofacial Langerhans Cell Histiocytosis Successfully Treated Through Intralesional Injection of Triamcinolone Acetonide: A Retrospective Study.
Li J, et al. J Craniofac Surg. 2025 Jul-Aug;36(5):e551-e555.
単一臓器型LCHに対する治療選択肢は、経過観察から化学療法まで多岐にわたる。これらの選択肢の中で、コルチコステロイド注射は、その利便性、臓器構造と機能の温存、合併症発症率の低さから魅力的である。頭蓋顔面LCHの治療に対するトリアムシノロンアセトニド(TA)の病変内注射の有効性を検討し、典型的な症例を提示することを目的とした。 2014年4月~202年5月までに中山大学病院口腔科でTAの病変内注入を受けた顎LCHの11例を対象とした。臨床病理学的データを収集し分析した。男性7例、女性4例で、年齢は14.6 ± 16.9歳であった。病変のほとんどは下顎骨であった(9例, 81.8%)。TAの病変内注入の有効率は90.9%であった。初期投与量と累積投与量は、それぞれ33.2 ± 21.0 mgと99.5 ± 88.7 mgであった。病変が完全に骨化するまでに要した期間は12.5 ± 8.2か月であった。追跡期間は20 ± 13.4か月であった。有効率は小児と成人で同程度であった(100% vs. 75%, P=0.364)が、初回投与量、累積投与量、注射回数、病変の完全骨化に要した時間は全て小児の方が低値であった(P<0.05)。結論として、TAの病変内注射は、特に小児の頭蓋顔面LCHに対する適切な治療選択肢である。今回の知見を検証するためには、より大規模な患者コホートを対象とした研究が必要がある。
6)「小児LCHの皮膚症状および組織学的特徴を解明するための多角的横断的記述研究」
An ambispective cross-sectional descriptive study to characterise the cutaneous and histological features of pediatric Langerhans cell histiocytosis (LCH).
Mondal A, et al. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2025 Jul-Aug;91(4):488-495.
【背景】LCHは、骨髄前駆細胞に由来する病的なランゲルハンス細胞を特徴とする特発性疾患である。その多様な皮膚症状および組織学的所見、予後予測に関するデータは十分ではない。【目的】LCH患児の臨床的および組織学的特徴を分析し、全身病変の頻度および重症度と、様々な臨床的および組織病理学的所見との関連を検証する。【方法】LCH の臨床的特徴と組織学的特徴を明らかにするために、三次紹介センターで2年間にわたる多角的横断的記述研究を実施した。20例(前方視的10例、後方視的10例)が皮膚生検の組織病理検査によりLCHと診断された。【結果】20例の年齢は大部分が1~5歳で、男性が多かった(75%)。最も多い症状は発熱(100%)で、次いで掻痒(65%)、腹痛(45%)、呼吸器症状(40%)であった。頭皮の病変を全例に認め、紅斑性丘疹が最も多かった(95%)。全身検索では、肝腫大(65%)、脾腫大(40%)、頸部リンパ節腫脹(50%)を認めた。様々な皮膚病変の組織病理学的評価により、ランゲルハンス細胞の密な真皮浸潤、乳頭状真皮浮腫、顕著な赤血球の血管外漏出が明らかになった。免疫組織化学によりランゲルハンス細胞が確認された。全身評価では、さまざまな率で臓器浸潤が示唆された。【限界】症例数が少なく、症例の半数が後方視的研究であることが、本研究の主な限界である。【結論】皮膚LCHでは、皮膚病変は多発することがあり、発熱は病歴や受診時に常に認められる特徴であり、LCHの臨床診断への重要な手がかりとなる可能性があることを示している。組織学的特徴に関しては、乳頭状真皮浮腫と赤血球の血管外漏出が顕著な所見である。組織病理学的特徴で、疾患の進行や全身病変の程度を予測できない。
7)「診断時の血液中BRAFV600E陽性単核細胞の存在は小児 LCH における治療抵抗性と神経変性症の予測因子となる」
BRAF V600E-positive mononuclear cells in blood at diagnosis portend treatment failure and neurodegeneration in pediatric LCH.
Lin H, et al. Blood. 2025 Jul 10;146(2):206-218.
LCHは、造血細胞におけるMAPK活性化によって引き起こされる骨髄腫瘍性疾患である。歴史的に、LCHは死亡リスクに基づき、「リスク臓器」(RO陽性:骨髄、肝臓、脾臓)の病期分類が行われてきた。支持療法の向上とMAPK経路阻害薬の有効性により、LCH患者が死亡することは稀となっている。しかし、多臓器型LCH患者の多くは現在の第一選択化学療法では治癒せず、治療抵抗性はLCH関連神経変性症(LCH-ND)を含む長期的な続発症と関連している。本研究では、LCHの小児385例と成人115例のコホートを対象に、中央値4年間(幅:0.02-18)の追跡調査を行い、発症時のLCHの病変、腫瘍の遺伝子変異、治療前の末梢血単核細胞(PBMC)と骨髄中のBRAFV600E変異が、全身および中枢神経系の転帰に及ぼす影響を評価した。5年無イベント生存率は小児コホートで50.7%、成人コホートで32.7%であった。小児では、BRAFV600E陽性PBMCの存在が第一選択治療の抵抗性と強く関連していた(ハザード比7.7)。注目すべきことに、診断時にBRAFV600E陽性PBMCが存在する例は、LCH-NDを発症するリスクが最も高かった(ハザード比23.1)。これらの知見は、LCH細胞の持続陽性と起源細胞が、病変の広がりと臨床リスクを決定するという小児LCH病因の最新モデルを裏付けている。したがって、小児LCH診断病期分類の大幅な改訂を提案し、歴史的な死亡リスクに焦点を当てるのではなく、病変部位、病変の遺伝子変異、末梢血中LCH細胞(例:BRAFV600E陽性PBMC)に基づいて、全身治療抵抗性やLCH-NDのリスクに焦点を当てることを提案する。
8)「TRK1再構成組織球症:臨床病理学的および分子学的特徴」
NTRK1-rearranged histiocytosis: clinicopathologic and molecular features.
Fragneau R, et al. Blood Adv. 2025 Jul 22;9(14):3617-3628.
Non-LCH組織球症は、多様な組織球性疾患群である。臨床的、組織病理学的、分子生物学的特徴に基づいて、様々な疾患群が定義されている。本研究は、NTRK遺伝子再構成型組織球症を定義することを目的とした。国際協同研究で、pan-TRK発現やインフレームNTRK遺伝子再構成を有する組織球症50症例を解析した。また、対照として45例の黄色肉芽腫をpan-TRK免疫組織化学およびRNAターゲットシークエンスにより解析した。組織標本の中央評価を行い、臨床データおよび分子生物学的データを収集した。50例のうち、30例が小児、20例が成人で、年齢の中央値は11.5歳(幅:0~73歳)、64%が男性であった。44例(88%)は皮膚限局型で、41例が単一皮膚病変、3例が多発皮膚病変であった。4例は、皮膚病変、肝腫大、輸血を必要とする血小板減少症を呈する新生児であった。残りの2例には、それぞれ、脳、気管支の生命を脅かす病変があった。全例で黄色肉芽腫の組織学的所見が見られ、泡状組織球や Touton 巨細胞を認める例が多かった。50例全てで組織球はpan-TRK染色陽性であったが、インフレームNTRK融合のない対照の45例の黄色肉芽腫は全てpan-TRK陰性であった。NTRK1融合パートナーとして、IRF2BP2(23/46例)、TPM3(12/46例)、SQSTM1(3/46例)、PRDX1(3/46例)、NPM1(2/46例)、LMNA(2/46例)、ARHGEF2 (1/46例)が同定された。臨床転帰は良好で、播種性病変のあった新生児の4例中3例で自然退縮が認められ、TRK阻害剤ラロトレクチニブを投与された脳病変、気管支病変の2例は迅速な臨床効果を認めた。本研究は、組織球症の分子生物学的特徴の解明を進展させ、患者の診断と個別化治療の指針となる可能性がある。
9)「黄色肉芽腫におけるNTRK融合遺伝子:23症例の臨床病理学的および分子生物学的解析」
NTRK Fusions in Xanthogranuloma, a Clinicopathologic and Molecular Analysis of 23 Cases.
Umphress B, et al. Am J Surg Pathol. 2025 Jul 1;49(7):639-645.
黄色肉芽腫は組織球性腫瘍の中で最も高頻度の疾患であり、臨床像として孤立性から多発性まで皮膚病変は多岐にわたり、頻度は低いものの播種性病変へ進展する例もある。孤発性病変が78%~81%を占める。免疫染色によりNTRK過剰発現を示す孤発性皮膚黄色肉芽腫の2例を経験し、RNAとDNAシークエンスの両方でNTRK1融合遺伝子の存在を確認した。さらに55例をpan-TRK免疫染色でスクリーニングしたところ、孤発性黄色肉芽腫の48例中26例(54 %)にTRK過剰発現を認めたのに対し、多発性または播種性黄色肉芽腫では7例全てでTRK過剰発現を認めなかった。孤発性黄色肉芽腫の23例遺伝子解析した。pan-TRK免疫染色が陽性であった16例の全てで、RNAとDNAシークエンスによりNTRK1融合の存在が確認された。免疫染色が陰性であった7例は全て、NTRK融合は確認されなかった。NTRK変異のない例と比較し、NTRK融合が確認された例は全て、NTRK1のRNA転写産物の過剰発現があり、平均58倍の増加を認めた(P=8.77x10-15)。さらに、融合遺伝子のある症例は全て、NTRK1の細胞外領域が欠損しており、融合パートナーはTPM3、PRDX1、IRF2BP2、LRRIP1、SQSTM1であった。DNAシークエンシングにより、DNAメチル化遺伝子であるDNMT3A・KDM5D・SETD2およびMTOR-PI3K経路遺伝子のFLCNに機能喪失変異が同定された。MTOR-PI3K経路遺伝子のPIK3CG・IL10Raおよび転写調節因子のPAX8にコピー数増加が認められた。NTRK1融合の頻度は、多発性および播種性黄色肉芽腫と比較して、孤発性黄色肉芽腫で著しく高かった(54% vs. 0%)。NTRK1融合遺伝子の頻度が孤発型と比較して多病変型で低かったことから、NTRK1融合遺伝子はMAPキナーゼ経路の点変異よりも腫瘍を多発型へと進展させる効率が低いことが示唆される。NTRK1融合遺伝子は他の組織球症ではまれであるため、pan-TRK免疫染色は、組織球性腫瘍における黄色肉芽腫の診断確定や、低リスクの黄色肉芽腫のスクリーニングに有用である可能性がある。
10)「韓国におけるLCHの遺伝学的背景の解明:変異プロファイルと臨床的相関からの包括的知見」
Unraveling the Genetic Landscape of Langerhans Cell Histiocytosis in Korean Patients: Comprehensive Insights from Mutational Profiles and Clinical Correlations.
Koh KN, et al. Cancer Res Treat. 2025 Jul;57(3):873-882.
【目的】LCH患者を対象に、MAPK経路の遺伝子変異の頻度、詳細な変異プロファイル、遺伝子変異と臨床的特徴・予後との相関に焦点を当て、包括的な遺伝子解析を行うことを目的とした。【患者と方法】病理学的にLCHと診断された45例のパラフィン包埋標本から抽出したゲノムDNAを用い、382個の癌関連遺伝子のエクソンのターゲット次世代シークエンシングを実施した。【結果】大多数(91.1%)の症例は単一臓器型で、最も高頻度の病変部位は骨(84.4%)であった。初期治療はさまざまで、中央値6.8年の追跡期間中に死亡例はなかった。遺伝子解析の結果、全患者にMAPK経路の変異が認められ、BRAF変異が51.2%、MAP2K1変異が42.2%、RAF1変異が4.4%、KRAS変異が2.2%であった。これらの変異は相互排他的であった。詳細な変異プロファイルから、BRAF変異例のうち18例が点変異、5例がインフレーム欠失があったのに対し、MAP2K1変異例ではほとんどがインフレーム欠失でミスセンス変異は1例のみであった。これまで報告されていない多様なBRAF、MAP2K1、KRASの点変異やLCHで初めてのRAF1-KLC1融合例を検出された。 MAP2K1変異は高齢患者により多く認められたのに対し、BRAFV600変異は孤発性骨病変の例に多かった。遺伝子変異は、高リスク因子や無イベント生存率とは相関しなかった。【結論】包括的な遺伝子解析により、全てのLCH患者において相互排他的なMAPK経路の変異が同定され、LCHの遺伝学的理解において包括的検査の重要性が浮き彫りになった。